インプラント治療を受けた後、骨造成が行われることがありますが、この過程で腫れや痛みが生じることがあります。
本記事ではインプラント治療の骨造成は腫れるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- インプラント治療における骨造成とは
- 骨造成の後に腫れる理由
- 骨造成のメリットとデメリット
インプラント治療の骨造成は腫れるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
骨造成とは

- インプラント治療における骨造成とは何ですか?
- インプラント治療における骨造成とは、顎の骨が不足している箇所に対して新しい骨を再生する治療のことです。骨造成は、抜歯後や歯周病によって骨が吸収された部分に行われ、インプラントを埋め込むためのしっかりとした土台を作ります。骨造成は、インプラント手術と同時に行う場合もあれば、事前に行うこともあります。治療を成功させるためには、患者さん一人ひとりの状態に応じた適切な診断と治療計画が重要です。骨造成を適切に行うことで、インプラント治療を効果的に進められるようになるとされています。
- 骨造成にはどのような種類がありますか?
- インプラント治療において、十分な骨量を確保するために必要な骨造成には、いくつかの治療法があります。以下で解説します。
- GBR法(骨誘導再生法)
GBR法は、骨の再生を助けるための方法で、特に歯周病や外傷により骨が不足した場合に使用されます。自家骨や人工骨を補填し、特殊な膜(メンブレン)で覆うことで、骨が誘導される仕組みです。 - サイナスリフト
サイナスリフトは、上顎骨の高さが不足している場合に行われる治療です。サイナスリフトでは、上顎洞の底を押し上げて骨補填材を挿入し、インプラントを埋め込むためのスペースを作ります。 - ソケットリフト
ソケットリフトは、上顎洞の底を上昇させて骨を再生させる方法で、治療が簡便で感染リスクが低いとされています。顎骨の高さが5mm以上ある場合に適用され、治癒期間が短いため、多くのケースで取り入れられます。 - 遊離骨移植(ゆうりこついしょく)
遊離骨移植は、自身の骨をほかの部位から採取し、骨が不足している箇所に移植する方法です。遊離骨移植は、骨がしっかりと定着するまで数ヶ月を要しますが、骨の安定性が高いため、効果が期待できる治療法として用いられています。 - ソケットプリザベーション
ソケットプリザベーションは、抜歯後に生じる骨の吸収を抑えるために行われる処置です。抜歯した部分に骨補填材を挿入し、骨が吸収されないように保護することが目的です。将来的にインプラントを埋め込むための準備として有効とされています。
- GBR法(骨誘導再生法)
- 骨造成にはどのくらいの期間がかかりますか?
- 骨造成に必要な期間は以下のとおりです。
- GBR法(骨誘導再生法):6~10ヶ月程度
- サイナスリフト:6~12ヶ月程度
- ソケットリフト:6~12ヶ月程度
- 遊離骨移植:4〜6ヶ月程度
- ソケットプリザベーション:3〜6ヶ月程度
骨造成後の腫れ

- 骨造成の後に腫れるのはなぜですか?
- 骨造成手術後に腫れが生じるのは、身体が手術による刺激に反応する自然な過程の一部です。手術中に組織が切開されたり、骨に負担がかかったりすることで、炎症反応が起こり、その結果、腫れや痛みとして現れることがあります。身体が治癒に向けて働いているサインです。特に上顎洞底挙上術(じょうがくどうていきょじょうじゅつ)では、上顎洞膜がとても繊細であるため、上顎の骨造成後に腫れが発生しやすくなります。また、骨造成を行う範囲が広いほど、腫れのリスクは高くなります。
さらに、年齢や性別に関係なく、腫れが生じやすい体質の方もいるとされています。
- 骨造成後に腫れはいつまで続きますか?
- 骨造成手術後、腫れが現れるタイミングとその持続期間には個人差があります。以下で解説します。【初期段階】
手術後24〜48時間以内に腫れが感じられるようになります。これは、手術による組織の刺激が原因で、身体が炎症反応を起こすためです。【ピーク時期】
腫れは、手術後2〜3日目に強くなることが多いようです。この時期は、腫れが強くなり、多少の痛みを伴うこともあります。【腫れが引く時期】
その後、腫れは徐々に引いていき、通常1週間以内にはほとんど消失するとされています。この段階では、身体の回復が進んでいるため、腫れは自然に軽減します。【腫れが長引く場合】
腫れが1週間以上続く、または時間が経つにつれて悪化する場合は、合併症が発生している可能性があるため、早急に歯科医師に相談することが重要です。また、腫れが出やすい体質の方もおり、年齢や性別に関係なく、個々の体調や反応により腫れの程度が変わることがあります。腫れは時間の経過とともに徐々に引いていきますが、必要に応じて治療後のケアを行うことで軽減できます。
- 骨造成後に腫れを軽減する方法はありますか?
- 骨造成手術後の腫れを軽減するためには、どのような方法があるのでしょうか。
以下で解説します。- 冷却療法
手術後最初の48時間は、冷却療法を行うことが腫れを軽減するために有効とされています。アイスパックや冷却ジェルを患部に20分間当て、その後20分間休むサイクルで繰り返し冷やしましょう。ただし、氷を直接皮膚に当てないようにタオルなどで包み、凍傷を防ぐようにしましょう。 - 頭部の高い位置で休む
寝るときには枕を高くして、頭部を心臓よりも高い位置に保つようにしましょう。これにより、血流が調整され、腫れを抑えられます。 - 処方された薬をきちんと服用
手術後には抗炎症薬や鎮痛剤が処方されることが多いため、指示どおりに服用しましょう。抗生物質が処方されている場合は、感染予防のために規定量を守って服用することが大切です。 - 安静に過ごす
休息を十分にとり、激しい運動や過度な労働は避けましょう。身体を休めることで回復を早め、腫れを軽減する助けになります。 - 食事の工夫
食事はやわらかいものを選び、固いものや辛い食べ物を避けるといいでしょう。また、冷たい食事を摂ることも腫れを抑える助けになります。水分補給もしっかり行い、体内の水分バランスを保つことも重要です。
- 冷却療法
- 骨造成後に腫れが強い場合や痛みがあるときはどうすればいいですか?
- 骨造成手術後に腫れや痛みが強い場合はどうすればいいのでしょうか?以下で解説します。【腫れや痛みが悪化する場合】
手術後に腫れや痛みが時間とともに悪化する場合や、強い痛みが持続する場合は、感染症やほかの合併症が発生していることが考えられます。このような場合は、自己判断で放置せず、すぐに歯科医師に相談しましょう。【発熱がある場合】
高熱が出る場合は、体内で感染が広がっている兆候です。発熱と同時に腫れや痛みが強くなっている場合は、感染が疑われるため、速やかに歯科医師に連絡し、指示を仰ぐことが大切です。【膿が出る場合】
手術後の傷口から膿が出る場合、感染が進行している可能性があります。この場合、すぐに歯科医師に連絡し、適切な処置を受けることが必要です。【そのほかの異常が現れた場合】
吐き気やめまい、出血が止まらないといった異常が現れた場合も、早急に歯科医師の診察を受けるのがおすすめです。これらは手術後の回復過程では見られない症状であり、早期に対応が求められます。そのほか、抗生物質や鎮痛剤が体質に合わない場合、湿疹や下痢が発生することがあります。その場合は、自己判断せずに早めに歯科医師に相談することが大切です。
骨造成のメリットとデメリット
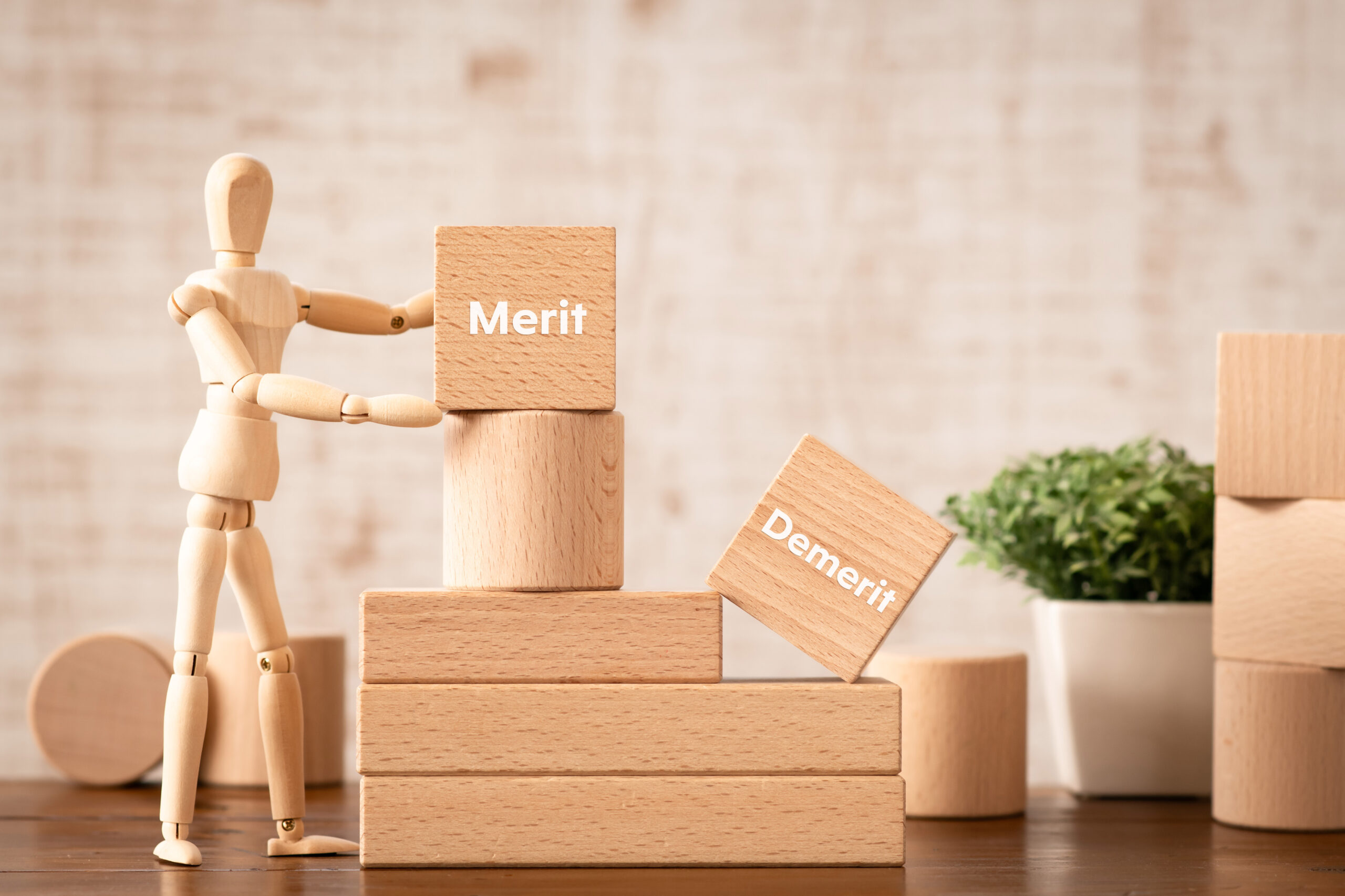
- 骨造成のメリットを教えてください
- 骨造成のメリットは以下のとおりです。
- 十分な骨量の確保
インプラントが骨を突き抜けたり、歯茎から露出したりといった問題を防ぐことができ、手術時のリスクを軽減した治療を進めることが可能になります。 - 長期的な安定性の向上
適切なケアを行えば、インプラントは長期間にわたって安定した状態で使用できます。 - 歯茎の調和が回復
骨造成によって十分な骨を確保することで、歯茎のバランスが整い、見た目の美しさを回復することができます。
- 十分な骨量の確保
- 骨造成のデメリットを教えてください
- 骨造成のデメリットは以下のとおりです。
- 治療期間が延びる可能性がある
骨造成を行うには外科手術が必要であり、自家骨や骨補填材が骨として再生するまで数ヶ月間の期間を要します。そのため、予定していた治療期間よりも長くなる場合があります。 - 骨造成が適さない場合がある
喫煙や全身疾患をお持ちの方は、骨造成後の治癒がうまく進まない可能性があります。
- 治療期間が延びる可能性がある
編集部まとめ

ここまでインプラント治療の骨造成は腫れるのかについてお伝えしてきました。記事の要点をまとめると以下のとおりです。
- インプラント治療における骨造成とは、顎の骨が不足している箇所に対して新しい骨を再生する治療のこと。抜歯後や歯周病によって骨が吸収された部分に行われ、インプラントを埋め込むためのしっかりとした土台を作る
- 手術中に組織が切開されたり、骨に負担がかかったりすることで、炎症反応が起こり、その結果、腫れや痛みとして現れることがある。身体が治癒に向けて働いているサインでもある
- 骨造成のメリットは十分な骨量を確保できたり歯茎の調和が回復したりすること。デメリットには治療期間が延びる可能性があったり骨造成が適さなかったりすることがある
インプラント治療における骨造成後の腫れは、回復過程の一部ですが、適切なケアを行うことで腫れの軽減が期待できます。冷却療法や休息、処方薬の服用を心がけ、必要に応じて歯科医師への相談が大切です。
腫れや痛みが長引く場合や異常を感じた場合には、早期に歯科医師のアドバイスを受けることをおすすめします。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
