インプラント治療では、失った歯を補うために人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を装着します。なかでもボーンレベルインプラントは、歯槽骨の高さにインプラントを埋め込む構造で、審美性や機能性に優れた選択肢のひとつです。特に前歯部など、自然な見た目が求められる部位において効果を発揮しますが、治療には注意点もあります。本記事では、ボーンレベルインプラントの基本的な特徴をはじめ、ティッシュレベルインプラントとの違い、適している患者さんの条件、さらにメリット・デメリットや治療の流れまで、わかりやすく解説します。
ボーンレベルインプラントの基礎知識
 ボーンレベルインプラント(Bone Level Implant)とは、インプラント体を歯槽骨の高さと同じ位置に埋入する手法で、歯茎の下にインプラントが完全に隠れる構造となっています。
ボーンレベルインプラント(Bone Level Implant)とは、インプラント体を歯槽骨の高さと同じ位置に埋入する手法で、歯茎の下にインプラントが完全に隠れる構造となっています。
このタイプは、天然歯の構造に近い形で人工歯を支持できるため、噛み合わせや見た目のバランスを重視するケースに用いられることが多い方法です。特に前歯部など審美的な配慮が求められる部位では、周囲の歯茎との調和が重要視されるため、ボーンレベルインプラントが選ばれやすい傾向があります。
ボーンレベルインプラントでは、インプラント体とアバットメントの結合部が歯槽骨の中に位置するため、細菌の侵入を防ぎやすい構造設計もされており、長期的な安定性に配慮された仕様です。ただし、骨の状態や歯茎の厚みなど、患者さんの個々の条件によって適応が変わるため、慎重な診査が必要です。
ボーンレベルとティッシュレベルの違い
 インプラント治療には、ボーンレベルインプラントとティッシュレベルインプラントの2種類があります。両者の主な違いは、インプラント体の埋入位置にありますが、それに伴って清掃性や審美性にも違いが生じます。
インプラント治療には、ボーンレベルインプラントとティッシュレベルインプラントの2種類があります。両者の主な違いは、インプラント体の埋入位置にありますが、それに伴って清掃性や審美性にも違いが生じます。
インプラントの位置
ボーンレベルインプラントは、インプラント体の上端が歯槽骨と同じレベル、つまり骨のなかに完全に埋まるように設計されています。これに対して、ティッシュレベルインプラントは、インプラントの一部が歯茎の上に出るように設計されており、アバットメントとの結合部が歯肉の上に位置します。
この違いにより、ボーンレベルインプラントでは補綴物(上部構造)の立ち上がりがより自然な歯の形に近づき、周囲の歯との調和をとりやすいという利点があります。一方で、埋入の際には歯槽骨と歯茎の厚みを慎重に確認し、深さの調整が必要となります。
手入れのしやすさ
ティッシュレベルインプラントは、インプラント体の上部が歯茎の外に露出するため、セルフケアやプロフェッショナルケアの際にアクセスしやすく、清掃性に優れている点が挙げられます。
一方で、ボーンレベルインプラントでは結合部が歯茎の下にあるため、患者さん自身によるプラークコントロールにはやや注意が必要です。治療後のメンテナンスをしっかり行うことで、インプラント周囲炎のリスクを抑えることができます。定期的な歯科医院でのメンテナンスに加え、歯間ブラシやデンタルフロスなど補助的な清掃用具を用いた丁寧なセルフケアが求められます。
審美性
審美的な仕上がりを重視する場合には、ボーンレベルインプラントが選ばれることが多くあります。特に前歯部では、歯茎のカーブや隣在歯との見た目の調和が求められるため、インプラント体の位置が骨内にあるボーンレベル型の方が自然な見た目を実現しやすいとされています。
歯茎の厚みや形態にもよりますが、ボーンレベルインプラントの方がティッシュレベルインプラントよりも歯茎が自然にフィットしやすく、歯と歯の間に生じるブラックトライアングルも目立ちにくくなる傾向があります。つまり、審美性を優先的に考えるならば、ボーンレベルインプラントが有利といえるでしょう。
ボーンレベルが適している方の特徴
 ボーンレベルインプラントが適しているのは、審美的な要求が高い部位や、自然な見た目にこだわりたい患者さんです。とくに以下のようなケースでは、このインプラントの使用が検討されます。
ボーンレベルインプラントが適しているのは、審美的な要求が高い部位や、自然な見た目にこだわりたい患者さんです。とくに以下のようなケースでは、このインプラントの使用が検討されます。
◎前歯部など審美領域でのインプラント治療
ボーンレベルインプラントでは、インプラントを骨内に埋め込むため、人工歯と歯茎の境界を自然に仕上げやすく、隣の天然歯との色味・形状のバランスをとりやすくなります。
◎骨量がしっかりと保たれている方
骨の高さや幅が不足している場合には、骨造成が必要になる可能性があります。骨の条件が良好である程、スムーズにインプラントを埋入することができます。
なかには、骨の状態が不十分であるにも関わらず、無理にボーンレベルインプラントを選択しようとするケースも見受けられます。しかし、骨の再生や歯茎の再建などの処置を適切に行わなければ、予後に悪影響を及ぼす可能性があるため、治療前の精密な診査と説明が欠かせません。
ボーンレベルインプラントのメリット
 ボーンレベルインプラントには、以下に挙げる3つのメリットを伴います。
ボーンレベルインプラントには、以下に挙げる3つのメリットを伴います。
自然な歯肉ラインを再現しやすい
ボーンレベルインプラントは、インプラント体を歯槽骨の高さに埋入する構造であるため、歯茎との境界が自然になじみやすい特長があります。補綴物の立ち上がりが天然歯の形態に近く、周囲の歯や歯茎との調和がとりやすいため、前歯部など審美性が求められる部位に適しています。
また、インプラント体とアバットメントの結合部が歯茎の下に隠れる構造となっていることで、治療後に歯茎のラインが不自然に見えることを防ぎやすく、患者さんの表情や笑顔に違和感が出にくい点も評価されています。特に、歯茎の厚みや形が整っている場合には、天然歯のような仕上がりを目指すことが可能です。
選択肢が豊富で幅広い症例に対応している
ボーンレベルインプラントは、各メーカーから多様なサイズ・形状が提供されており、埋入する部位の骨幅や高さ、咬合状態に応じて柔軟に選択できる利点があります。顎の骨が十分にある症例ではもちろんのこと、骨造成を併用すればある程度骨量の不足した症例にも対応できます。また、角度付きアバットメントやカスタムアバットメントを活用することで、傾斜のある骨や歯並びの調整が求められる症例にも適応可能です。
ボーンレベルインプラントのデメリット
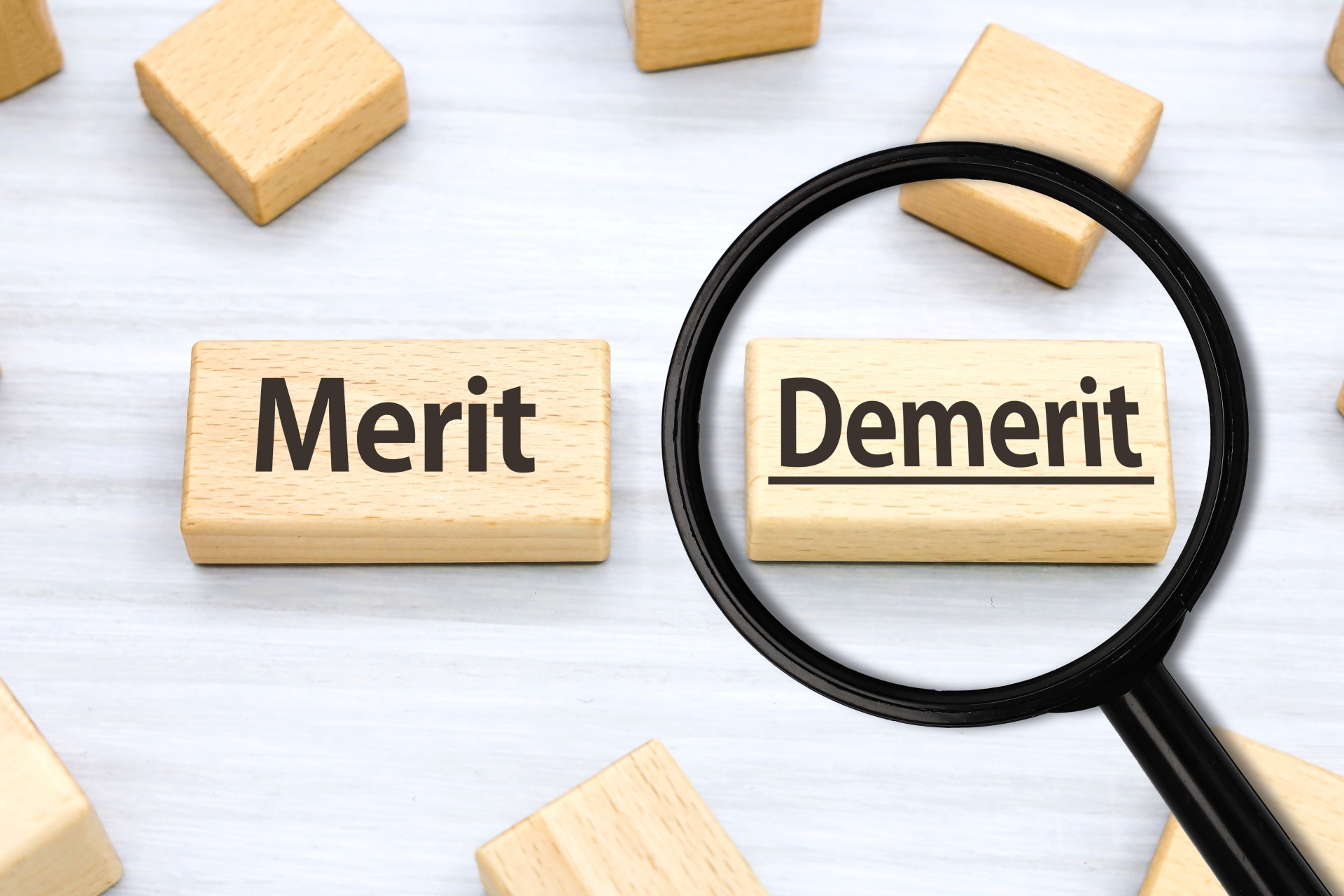 ボーンレベルインプラントには、以下に挙げる3つのデメリットを伴います。
ボーンレベルインプラントには、以下に挙げる3つのデメリットを伴います。
骨吸収につながりやすい
ボーンレベルインプラントでは、インプラント体の結合部が歯槽骨の内部に設置されるため、微小な動きや咬合力が骨に直接伝わりやすくなります。この刺激が慢性的に骨にかかることで、骨の減少が進行してしまうケースもあります。
特に、初期の骨結合が不十分であったり、咬合バランスが崩れていたりする場合には、局所的な力の集中によって骨の吸収が加速することがあるため注意が必要です。補綴設計の段階で噛み合わせの調整を丁寧に行うとともに、治療後の定期検診で骨の状態を確認していくことが重要です。
歯茎が薄いと金属が透けて見える可能性がある
前歯など審美性が要求される部位において、歯茎の厚みが少ない患者さんでは、インプラント体の金属色が歯茎を通して透けて見えることがあります。これをグレーアウトと呼ぶこともあり、審美性の低下につながる要因になります。
とりわけ上顎前歯部では、笑ったときに歯茎が大きく見える方も多いため、こうした審美上のリスクを事前に診断し、必要に応じて歯茎のボリュームを増やす処置(軟組織移植など)を併用することが検討されます。治療前の歯茎の厚みや骨の位置を把握したうえで、埋入の深さやインプラントの材質を調整することが望まれます。
手術の準備に時間がかかる
ボーンレベルインプラントは、構造が骨内に深く埋入されるため、術前の診査・診断において高い精度が求められます。歯槽骨の厚みや高さ、隣在歯との距離、咬合関係などを事前に詳細に把握する必要があり、CT撮影や三次元シミュレーションなどの画像診断を駆使して、治療計画を立てることが一般的です。
また、骨造成や歯茎の再建が必要な症例では、手術の前段階として前処置を行う必要があり、全体の治療期間が長くなることもあります。こうした準備を怠ると、術後にインプラント周囲炎や補綴トラブルなどのリスクが高まる可能性があるため、診査から埋入、補綴までを総合的にとらえて計画的に進めることが求められます。
ボーンレベルインプラントの治療の流れ
最後に、ボーンレベルインプラントの治療の流れを紹介します。
術前検査と三次元シミュレーション
治療の第一歩は、患者さんのお口全体の状態を精密に把握することから始まります。歯科用CTや口腔内スキャナーなどのデジタル機器を用いて、顎の骨の高さや幅、骨密度、歯茎の厚み、さらには噛み合わせのバランスまで立体的に解析します。これにより、インプラント治療に必要な解剖学的情報を正確に収集することが可能になります。
続いて、収集したデータをもとに、専用のソフトウェアで三次元シミュレーションを実施し、インプラントの適切な埋入位置や方向、深さを事前に設計します。これにより、治療後の補綴物との調和やメンテナンスのしやすさまで見据えた、科学的根拠に基づく治療計画が立てられます。なかには、骨量の不足や歯茎の厚みが不十分なケースもあり、その場合は骨造成や歯肉移植などの前処置を含めた計画が立案されます。
一次手術
治療計画に基づき、局所麻酔下で一次手術を行います。歯茎を切開して骨を露出させたのち、専用のドリルで慎重にインプラント体を埋め込むための穴を形成します。ここで重要なのは、三次元シミュレーションで設計した通りの位置と角度を正確に再現することです。
インプラント体を骨内に埋入したあとはカバースクリューを装着して、インプラントと骨が結合するのを待ちます。このオッセオインテグレーションと呼ばれる骨結合の期間は、一般的に2~4ヶ月程度で、部位や骨の状態により個人差があります。
二次手術、ヒーリングアバットメント装着
インプラントと骨との結合が確認された段階で、二次手術を行い、歯茎を再び切開してインプラント体の頭部を露出させます。この際、ヒーリングアバットメントと呼ばれる筒状のパーツを装着し、歯茎に人工歯を支えるための形を形成していきます。
ヒーリングアバットメントの目的は、歯茎と補綴物との境界部分を自然な形で整えることにあり、審美性と清掃性の両立に直結します。この工程には1〜2週間の治癒期間を設け、歯茎が安定するのを待ちます。特に前歯部などでは、このステップが最終的な見た目を大きく左右します。
上部構造装着
歯茎の形状が整ったのち、最終的な人工歯(上部構造)を作製するための型取りを行います。咬合関係や隣在歯との調和、清掃のしやすさを考慮して設計された補綴物は、ジルコニアやセラミックなどの審美性・耐久性に優れた素材から選択されます。
装着時には、細かな咬合調整を行い、噛み合わせが適切にとれているかを慎重に確認します。必要に応じて仮歯を併用しながら、色調・形態・機能のすべてにおいて患者さんにとって必要となる補綴物を完成させていきます。
定期メンテナンス
インプラント治療において、治療後の定期メンテナンスは欠かせないプロセスです。インプラントはむし歯こそ起こしませんが、周囲の歯茎や骨に炎症が起こるインプラント周囲炎を防ぐには、継続的な管理が不可欠です。
特にボーンレベルインプラントでは、インプラントとアバットメントの接合部が歯茎のなかにあるため、目に見えない部分に炎症が生じていても患者さん自身では気付くことが難しいことがあります。歯科医院での定期的なチェックによって、歯茎の状態、骨の吸収の有無、噛み合わせの変化、清掃状態を評価し、必要に応じてクリーニングや咬合調整を行います。
また、患者さんご自身によるセルフケアも重要です。歯間ブラシやフロスを活用し、インプラント周囲の清掃を丁寧に行うことで、長期的なインプラントの安定につながります。すべてのプロセスが終わった後も治療は続いているという意識をもち、歯科医院と連携しながらメンテナンスを継続していくことが求められます。
まとめ
ボーンレベルインプラントは、歯槽骨の高さにインプラント体を埋入することで、周囲の歯や歯茎との自然な調和を実現しやすい治療法です。選択肢の幅が広く、審美性や機能性の向上に貢献しますが、骨吸収による影響、術前の準備に時間がかかる点なども理解しておく必要があります。ボーンレベルインプラントによる治療を成功に導くには、精密な診断と適切な術後管理、そして継続的なメンテナンスが不可欠です。ボーンレベルインプラントに関心のある方は、まずは信頼できる歯科医院で詳しく相談してみましょう。
参考文献
