一般的にインプラントは10年以上使用できるといわれますが、あくまで平均的な年数であり個人差が大きいです。
インプラントは一度入れたら永久に使えるというわけではありません。インプラントの耐用年数はさまざまな要因によって変わります。
インプラントの耐用年数を延ばすには、定期的な検診やクリーニングを受ける必要があります。
ではインプラントの寿命がきたらどうしたらよいのでしょうか。
そこで、インプラントの平均寿命・再手術となるとき・そのときにかかる費用などについて解説しますので参考にしてください。
インプラントの寿命がきたら?

インプラントの寿命を考える上で、10年生存率という考え方が参考になります。
個人差はありますが10年経過した後もインプラントは約90%以上が生存しています。
ブリッジの10年生存率は約90%、義歯は約50%といわれますので、他の治療法よりも長期間使用することが可能です。
メンテナンス次第で長期にわたり使用できたケースもあるようです。しかし、インプラントは一度入れたら永久に使えるというわけではありません。
インプラントの寿命がきたらもう一度手術を受けるか、ブリッジや入れ歯に変更することになります。
再度インプラントの治療を受ける
インプラントが脱落する原因は、インプラント周囲炎・破損などです。喫煙習慣があったりメンテナンスを怠ったりすると、インプラントの生存率は低くなることがあります。
インプラントが寿命になった場合は再手術が必要です。インプラントの除去や骨組織の再生が必要です。
歯医者で定められている保証期間内であれば、無料で再手術を受けられます。ただし、患者さん側に原因がある場合は保証が効かないこともあります。
ブリッジや入れ歯に変更する
ブリッジは失った歯の両隣の歯を削って被せ物をかぶせその間に人工の歯をつなげる方法です。
利点は見た目が自然で噛み合わせがよくなり入れ歯と違って外れる心配がないことです。欠点は両隣の歯を削る必要があることです。
保険適用のブリッジは1割~3割負担で比較的安価に作成できます。自費診療の場合、セラミックなどの素材を選択できます。
審美性に優れ、耐久性に優れた素材を選択できるのが自費診療のブリッジのメリットです。保険適用なら1本あたり1〜2万円(税込)程度のものが多いです。しかし1本5~15万円(税込)程度かかるなど、費用が高額になる傾向があります。
入れ歯は失った歯や噛み合わせを補うために作られる人工の歯のことです。
部分入れ歯と全入れ歯の2種類があり、自分の口に合わせてオーダーメイドで作られます。適切なケアをすれば長く使えますが定期的なメンテナンスや調整が必要です。
それぞれの利点と欠点を比較しながら変更の有無について決めることが大切です。
インプラントの平均寿命はどのくらい?

インプラントは適切なメンテナンスを行うことで、10年生存率を上げることができます。一般的に約10年~15年は使うことができるとされています。
ほとんど10年保証がついていて、治療後に適切なケアを継続して少なくとも10年は持たせることが可能です。
これはあくまで目安で、ケアの状況により5年で寿命を迎えたり20年経っても問題なく使い続けられたりします。
過去には、患者さんがお亡くなりになるまで40年間インプラントを使い続けたという事例もあるくらいです。寿命の基準は一般的に普通に使用していて自然に外れてしまった状態をいいます。
上部構造が消耗した場合は交換すればまた使い続けることが可能です。
インプラントを10~15年残せる確率は?
厚生労働省の「歯科インプラントの治療のためのQ&A」によると、インプラントを10年~15年残せる確率は上顎の場合約90%下顎では約94%です。
また、抜歯直後に埋入した場合や骨移植をともなった埋入の場合は、約87%~92%という調査結果となっています。
ただし、この寿命はあくまで平均的なもので、セルフケアや口内環境によって10年持たない場合や15年以上持つ場合もあります。
挿入部位や生活習慣などでも変化する
インプラントの10年生存率は、挿入部位や生活習慣などによっても変化します。
適切なメンテナンスを行うことで、インプラントの寿命は一般的に約10〜15年といわれています。
インプラントの状態が悪くなる原因は歯周病です。正確には「インプラント周囲炎」といいます。
歯周病と同じような症状がでます。インプラントにした部分は細菌に感染しやすく、神経などがないため、症状がでても気づきにくいです。
そのため進行が早く、気づいたら重症化していたというケースもあります。
インプラント周囲炎予防のセルフケアとして、歯ブラシだけでなく歯間ブラシ・フロス・マウスウォッシュなどを併用しましょう。
しかし、インプラントはセルフケアだけでは限界がありますので、定期的に歯科医院に通いクリーニングとメンテナンスを受けてください。
こうすればインプラントの生存率を上げるだけでなく、万が一異常があっても早い段階で対処できます。
インプラントの再手術はどのように行うの?

インプラントの破損原因は、インプラント周囲炎・破損などです。
インプラントが破損したら調整や簡単な修理で対応できるレベルなのか確認が必要となります。
撤去や再治療になるのはインプラント周囲炎を起こしている場合が大半です。
顎の骨がインプラントを支えきれない場合は、その破損状態によって対処も変わってきます。
人工歯の破折やヒビは、インプラント体に何も問題がなければ上部構造だけ外し人工歯部分を修理することが可能です。
人工歯と連結部の緩みは調整で済むこともありますが、破損している場合はその部分の修理と調整を行います。
インプラント体からぐらぐら揺れている場合に必要なのは、インプラント周囲炎の有無・顎骨や周辺組織の確認・原因の特定です。
撤去か再治療かを診断して再治療になる場合、再手術は初めの手術と同様に顎の骨にインプラントを埋め込むことになります。
再手術を行う場合の費用

再手術を行う場合は、使用してきたインプラントを取り除いて再び欠損治療を行うことが必要です。
インプラントの治療の費用は、診察や手術などが医療保険の対象外となるため原則として全額自己負担となります。
一般的に、インプラントの治療費は全体で30万~50万円(税込)くらいです。
ただし、クリニックによって、また使用するインプラントの種類・口の中の状態などによって異なります。
なお、医院やインプラントメーカーの保証により無料で再手術が受けられる場合もあるようです。
保証期間内なら無償で再手術が可能

歯科医院の保証により無料でインプラントの再手術が受けられる場合もあります。
保証の内容や条件は歯科医院によって違うことがありますので治療前に確認しておきましょう。
インプラントを長期間使い続けられた場合は保証期間が過ぎていて費用を負担することになります。
保証期間を5年~10年と設定している歯科医院が多いですが、3年保証の歯科医院もあるようです。
適用には条件を満たす必要があるため注意
保証部位が脱落または破折した場合に歯科医療機関が無償で再治療を行います。
保証対象部位となるのは保証対象である埋入インプラント体および上部構造であり、保証書に埋入部位として記載されたものです。
適応条件は各クリニックが独自にか、第三者保証期間が定めています。
インプラントの寿命を延ばすために注意すべきこと
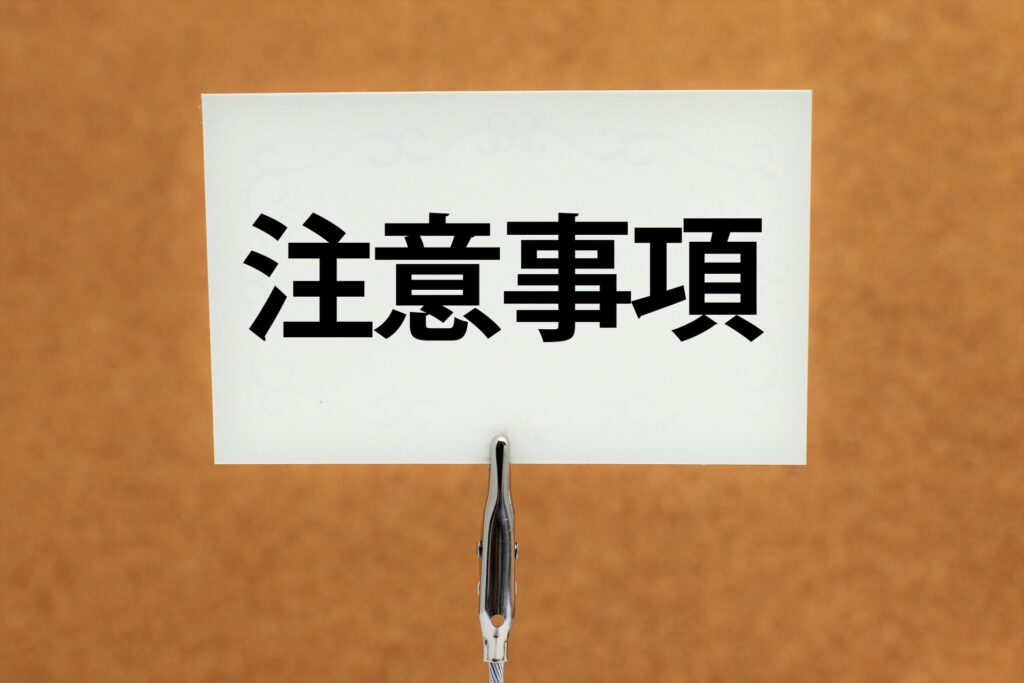
インプラントは適切なメンテナンスを行うことで、一般的に約10年~15年程度は使えるといわれています。
ただし、患者さんの生活習慣などによっては数年で寿命がくることもあれば、15年以上長持ちすることもあるようです。
定期的なメンテナンスの不履行・喫煙習慣・歯ぎしりや食いしばりなどがあると寿命は縮まります。
インプラントの生存率を上げるためには、セルフケアの徹底や定期的なメンテナンスがとても大切です。
定期的に歯科医院でメンテナンスを行う
インプラントを長く使い続けるには地道にメンテナンスすることが必要となります。インプラントはむし歯の心配はありませんが、歯周病と似たインプラント周囲炎への対策が重要です。
毎日行うセルフケアで口腔を清潔に保つことができれば、インプラントの寿命が短くなるのを抑えられます。
しかし、セルフケアだけでは限界がありますので、歯科医院でしっかりチェックすることが大切です。
メンテナンスでは主に、インプラント周囲炎の有無・噛み合わせ・インプラントの動揺度・歯周ポケットの深さがチェックされます。
メンテナンスは3ヶ月〜半年に一度くらいで、寿命が大きく違ってくる有益な手術後のケアです。
セルフケアをしっかり行う

インプラントはメンテナンスを怠ると清掃が行き届かなくなり、周囲に歯垢が溜まりやすくなります。
歯垢が溜まるとその中でさまざまな細菌が増殖し、周囲組織が細菌に感染するインプラント周囲炎が引き起こされるのです。
インプラント周囲炎の症状が進むとインプラントを支える歯槽骨が破壊されます。
歯肉の退縮や人工歯根の露出が始まり、最悪の場合に起こるのがインプラントの脱落です。インプラントの寿命を延ばすためにはインプラント周囲炎を防ぐことが必要となります。
セルフケアは予防の基本であり、毎日の正しいブラッシングが大変重要です。歯ブラシは自分の口に合ったものを選びましょう。歯ブラシは毛先が広がってきたら交換してください。
歯ぎしりや食いしばりに注意する
歯ぎしりや食いしばりの習慣があると、インプラント体やセラミック製の上部構造に過剰な負担がかかります。
インプラントには歯根膜というクッションになる部分が存在しないために、噛む力が直接加わるのです。
歯ぎしりを強くしている人の歯を見ると、削れている部分が認められます。歯ぎしりで天然歯がダメになった場合はインプラントを行っても同様の可能性が高いのです。
治療前はもちろん治療後に歯ぎしりや食いしばりをするようになった場合も、できるだけ早く改善した方がよいでしょう。
喫煙を控える

たばこの煙には何千種類もの化学物質が含まれています。有害物質は主にニコチン・タール・一酸化炭素が多いです。
口腔は煙が最初に触れる場所です。口腔内に入ったたばこの煙・成分は粘膜・歯茎から吸収されます。
たばこの有害物資の影響で血管が収縮するため、歯茎の血流量が減少します。血液循環が悪くなると、歯茎に十分な酸素が行き届きません。
酸素が行き届かないと、歯周病の原因となる細菌が繁殖しやすくなります。
歯周病になると腫れや出血などの症状がでますが喫煙者の場合、血行不良になっているためそれらの症状が出にくいです。歯周病の治療効果は低く、治りも悪いとされています。
たばこの有害物質が歯茎に与える悪影響はインプラント治療にも関係してきます。
傷口の治りが悪かったり、インプラント体と骨の結合がうまくいかなかったりなどのトラブルが起こる可能性があるのです。
そのため、インプラント治療中は禁煙が求められる場合もあります。
安全性の高いメーカーのインプラントを選ぶ
インプラントを選ぶ場合、安全性の高いメーカーのインプラントを選ぶようにしましょう。
有名メーカーのインプラントのメリットは多くの研究がされていることと、他の歯科医院に転院したときもそのメーカーのパーツがあることなどが挙げられます。
国内で受けるインプラントの治療では主に厚労省認可の製品が使用されています。しかし、患者さんの同意があれば歯科医師の責任の下でインプラントの輸入と使用が認められています。
未認可のインプラントを使った治療については、メリット・デメリット・リスク・トラブル対応などをよく検討してください。
世界で使用されているインプラントは歴史が深いものや浅いものなどさまざまです。たとえ一見してよく見えても、治療によって得られる効果や仕上がりの良し悪しには大差が生まれることもあります。
寿命を過ぎたインプラントを使い続けるリスクは?
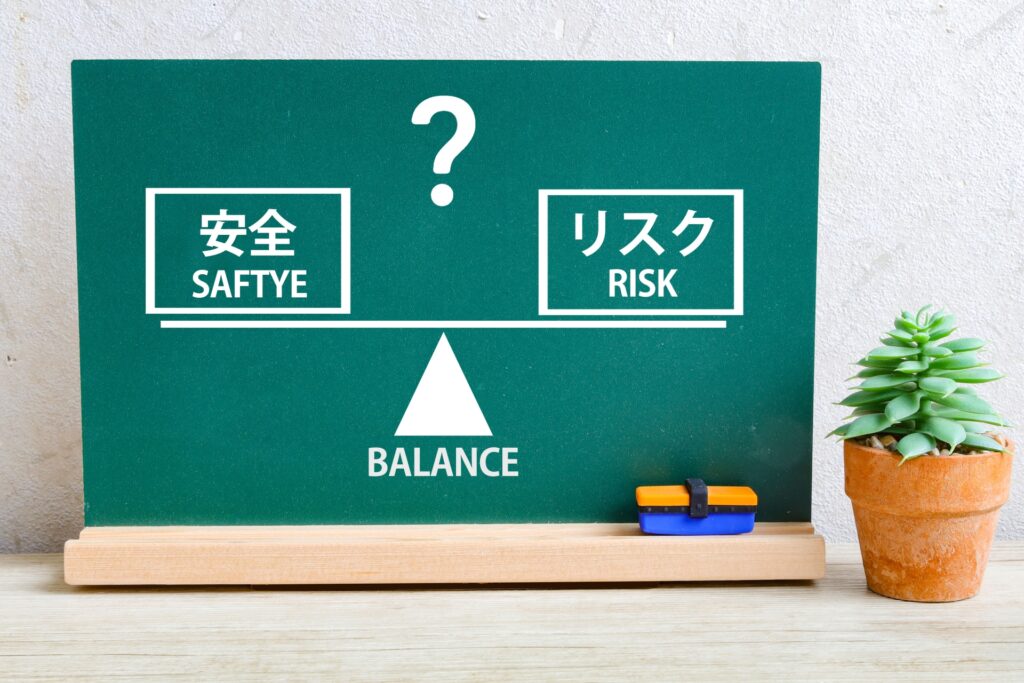
インプラントの10年生存率が過ぎるとそのインプラントの脱落などが生じることがあります。
そのため、再度インプラントの治療をするか入れ歯やブリッジなどの治療に変更するかの選択になります。
インプラントの人工歯が折れた・インプラント体が抜けそうになっている・インプラントがグラグラしているなどの状態で使い続けるとさまざまなトラブルが起こる可能性があります。
インプラントが使えなくなったり痛みが出たりするでしょう。
状況によっては次のインプラントの治療ができなくなることもあります。放置するとインプラント周囲炎によってインプラント周囲の顎の骨が溶けてしまうためです。
顎の骨が溶けてしまうと、次のインプラント治療のときに骨が足りず治療が難しくなる可能性もあるでしょう。
周囲の歯に影響が出ることがある
使えなくなったインプラントをそのままにしておくと、周囲の歯に影響が出ることもあるでしょう。
天然歯は歯と歯茎の境目を歯周ポケットと呼ぶのに対し、インプラントではインプラント周囲溝と呼ばれます。
インプラント周囲疾患にはインプラント周囲粘膜炎とインプラント周囲炎が含まれます。
また歯周組織と顎の骨は隣同士の歯とつながっています。そのため、隣の歯の歯茎に影響を与えるリスクもあります。
インプラントが使えず隣の歯に噛んだときの力が集中するため、歯並び・嚙み合わせが悪くなる場合もあるでしょう。
痛みが出ることがある
インプラントがグラグラしている状態で使い続けたり、歯茎が炎症を起こしていたりすると痛みが出ることもあります。
インプラント周囲炎が原因の場合、そのままにしておくと病巣が広がる可能性もあります。そうなると、歯茎・歯槽骨などの歯周組織に酷いダメージを与えるでしょう。
インプラントが使えないまま放置すると、上手く噛めなくなるなど、食生活にも影響を与える場合もあります。上部構造の破損は、上部構造の修理でまた使えるようになることもあります。
インプラントが使えなくなってきたと感じたら、歯科医院に相談しましょう。
まとめ

今回は、インプラントの生存率を少しでも上げる方法・使えなくなったインプラントを使い続けるリスク・再手術・ブリッジや入れ歯の使い方などについて触れてきました。
インプラントは一度入れたら永久に使えるというわけではありません。もしインプラントの寿命がきたらもう一度手術を受けるか、ブリッジや入れ歯に変更することになります。
インプラントの寿命がきたらどうすべきかお考えになる上で、ぜひこの記事を参考にしてください。
参考文献
- インプラントの咬合付与について|公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 禁煙宣言|公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- インプラント周囲炎の発現のメカニズム|公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会・日本歯周病学会 インプラントのメインテナンスに関する学会見解
- よくあるご質問|公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- インプラント|日本歯科医師会
- あなたの歯科インプラントは大丈夫ですか-なくならない歯科インプラントにかかわる相談-|独立行政法人 国民生活センター
- 安心してインプラント治療を受けるために
- 厚生労働省委託事業「歯科保健医療情報収集等事業」歯科インプラント治療のためのQ&A
- インプラント周囲疾患|特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
