インプラント治療は、失った歯を補う機能的かつ審美的な手段として広く行われていますが、正確な診断と手術技術が求められる高度な治療でもあります。なかには、インプラントが顎の骨を突き抜けて周囲の組織に障害を与える貫通トラブルが発生するケースもあり、出血や痛み、神経障害、副鼻腔炎などの深刻な合併症を伴うことがあります。本記事では、こうしたインプラントの貫通トラブルが起こる原因やリスク部位、症状、そして問題が生じた場合の適切な対処法や治療法について、医学的な観点から詳しく解説します。
インプラントが骨を貫通する原因
 はじめに、インプラント治療で人工歯根が顎骨を貫通する原因について解説します。
はじめに、インプラント治療で人工歯根が顎骨を貫通する原因について解説します。
顎骨の骨量不足
インプラント治療では、人工歯根となるチタン製のネジを顎の骨に埋め込む工程があります。このとき、十分な骨量や骨の厚みが確保されていないと、埋入したインプラントが顎骨を貫通してしまうリスクが高まります。特に長期間にわたり歯を失った状態が続いていた場合、骨が吸収して薄くなっているケースが少なくありません。骨の吸収は上顎・下顎ともに見られますが、とりわけ上顎では上顎洞の存在により骨の厚みが確保しづらくなっており、慎重な診断が求められます。また、骨粗しょう症などで骨密度が低下している場合も、同様にインプラントの安定性が確保しにくく、貫通リスクが高まるため注意が必要です。
医師の技術不足や検査の不備
インプラントの埋入は精密な手術であり、術前の画像診断と治療計画が極めて重要です。術前検査が不十分であったり、CT画像の読影や骨の評価が甘かったりした場合には、インプラントが意図せず骨を突き抜けてしまうことがあります。また、埋入角度や深度の見極めが不適切なまま手術が行われた場合、骨の外へと突き出てしまうこともあります。これらの要因は、執刀医の経験不足や技術的な未熟さに起因することが多く、患者さんにとっては深刻なトラブルにつながりかねません。そのため、インプラント治療を受ける際は、CT撮影などの精密検査が実施されているかどうか、また担当する歯科医師の経験や治療実績も確認しておくことが望ましいといえます。
貫通トラブルが起こりやすい部位
 インプラント手術で人工歯根の貫通トラブルが起こりやすいのは、以下の3つの部位です。
インプラント手術で人工歯根の貫通トラブルが起こりやすいのは、以下の3つの部位です。
上顎洞
上顎の奥歯の部分にインプラントを埋入する際、注意すべきなのが上顎洞(じょうがくどう)です。これは鼻の横に広がる空洞であり、上顎の骨のすぐ上に存在しています。骨の厚みが足りない場合や、上顎洞までの距離を正確に把握できていない状態でインプラントを埋め込むと、スクリューが上顎洞内に突き抜けてしまう恐れがあります。その結果、上顎洞の粘膜を傷つけたり、細菌感染を引き起こして上顎洞炎を発症したりするリスクが生じます。こうしたトラブルを防ぐには、必要に応じてソケットリフトやサイナスリフトなどの骨造成手術を行うことが推奨されます。
下顎管
下顎の奥歯付近には下顎管(かがくかん)と呼ばれる神経と血管が通る管があります。このなかには、下歯槽神経(かしそうしんけい)という知覚神経が通っており、誤ってこの管を損傷すると、顎や唇にしびれや感覚異常が出ることがあります。CT画像で下顎管の位置を正確に把握しないままインプラントを埋入すると、スクリューが下顎管を貫通し、神経を直接圧迫、損傷してしまう可能性があります。これは患者さんにとって大きな苦痛を伴い、長期的な後遺症につながるおそれもあるため、注意深い診査・診断が欠かせません。
鼻腔底穿孔
前歯部のインプラントでは、鼻腔底穿孔(びくうていせんこう)と呼ばれるトラブルが起こることもあります。これは、上顎の前歯にインプラントを埋入した際、スクリューが鼻腔の底にまで達してしまう状態です。鼻腔底はとても薄い骨に覆われているため、インプラントを想定よりも深く埋入することで、貫通するリスクが高まります。このような事態になると、鼻血や鼻腔への違和感、炎症症状などが現れやすくなり、場合によっては再手術が必要になることもあります。前歯部は審美性が問われる部位であるとともに、解剖学的な制約も多いため、術前の慎重な判断が重要です。
インプラントの貫通トラブルで現れやすい症状
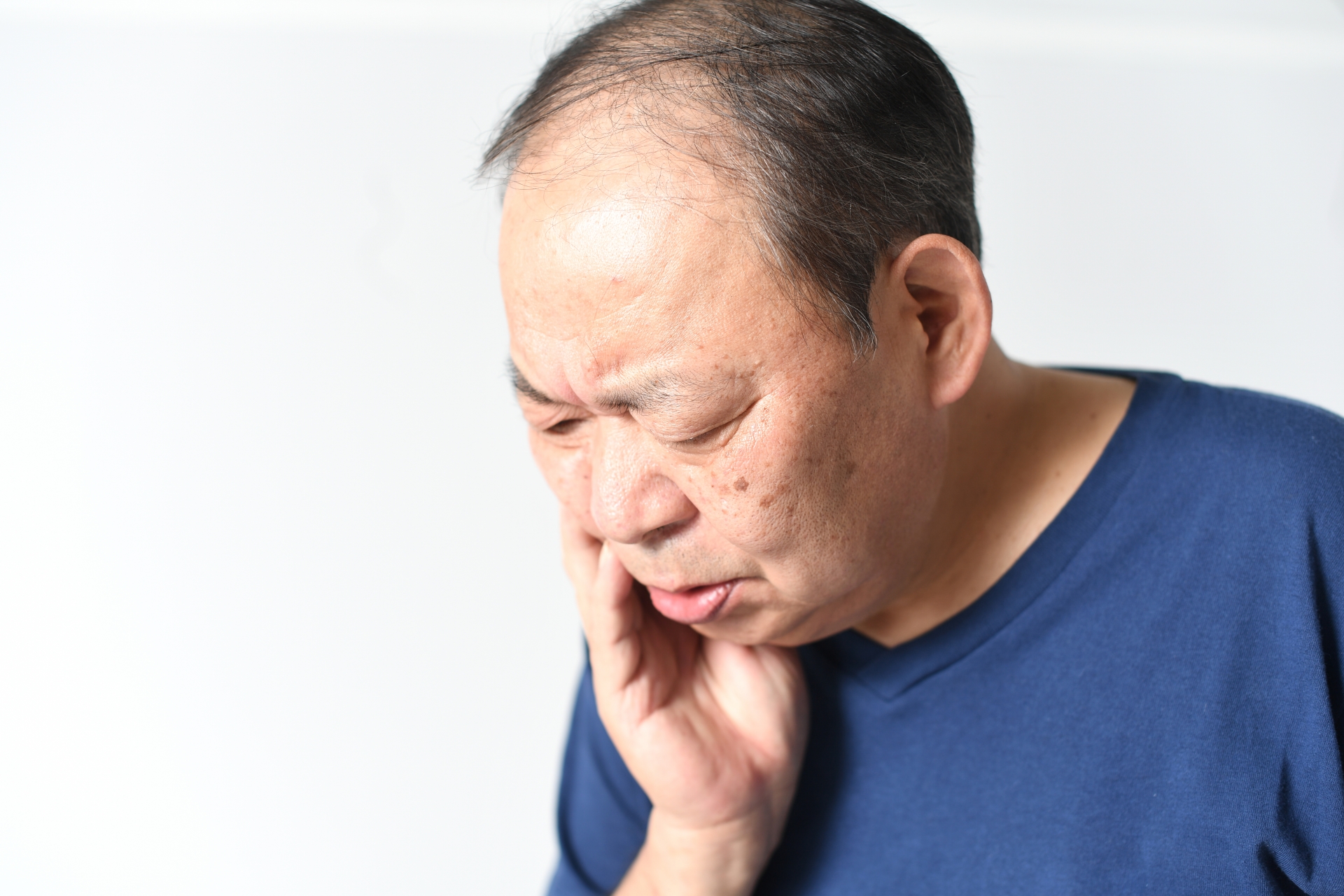 インプラント手術で貫通トラブルが起こると、次に挙げるような症状が現れやすいです。どの症状が現れるかは、インプラントが貫通した部位や重症度によって変わります。
インプラント手術で貫通トラブルが起こると、次に挙げるような症状が現れやすいです。どの症状が現れるかは、インプラントが貫通した部位や重症度によって変わります。
出血と強い痛み
インプラントが予定より深く埋入されて骨を突き抜けた場合、術中または術後に鋭い痛みや出血が生じることがあります。インプラント治療後の一時的な不快感や微量の出血は自然な反応ですが、明らかに出血量が多い、あるいは強い痛みが長時間持続する場合は異常のサインととらえるべきです。
特に、血管や神経の損傷が関与していると考えられる場合には、継続的な出血や痛みに加えて、腫脹や内出血、感覚異常が併発することもあります。過度の機械的刺激が血管壁に加わると、仮性動脈瘤や血腫の形成に至るリスクもあるため、安易に放置すべきではありません。インプラントの早期除去や外科的介入、薬物療法が必要となります。
膿が出る
インプラントが骨を貫通して上顎洞などに露出している場合、その周囲の組織に細菌が侵入し、感染を引き起こすことがあります。感染が進行すると、歯茎や上顎洞、鼻腔などから膿性の排出物がみられ、痛みや腫れを伴うこともあります。 この状態は、細菌の繁殖によって慢性化しやすく、一般的な抗菌薬だけでは根治が難しいこともあります。進行するとインプラント周囲炎を発症し、インプラント体の動揺、骨吸収、さらには脱落に至る可能性があります。
膿の排出は、免疫反応の一環として感染部位から炎症性滲出液が排出されているサインであり、軽視すべきではありません。局所の洗浄、感染源の除去、場合によってはインプラントの撤去が検討されるケースもあります。
知覚麻痺やしびれ
下顎の臼歯部にインプラントを埋入する際、下顎管に走行する下歯槽神経を損傷すると、顎や唇、舌の一部にしびれや麻痺が生じることがあります。このような症状は知覚麻痺または神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせいとうつう)に分類され、損傷の程度によっては数ヶ月以上にわたって症状が残る場合があります。
神経への損傷は、直接的な機械的圧迫、炎症性浮腫、もしくは神経周囲の血流障害によって引き起こされます。軽度な神経圧迫であれば、インプラントの除去や圧迫の解除により回復が見込めますが、神経線維の断裂や壊死がある場合は、症状が永続化することもあります。
上顎洞炎
インプラントが上顎洞に貫通すると、その刺激により上顎洞の粘膜が炎症を起こし、上顎洞炎が発症することがあります。上顎洞は副鼻腔のひとつであり、正常であれば吸気の加湿や加温などを担っています。インプラントが上顎洞の粘膜を刺激したり、感染源となる細菌が侵入したりした場合、炎症によって粘液が貯留し、圧痛や頬部の鈍痛、膿性鼻汁、頭重感などの症状が現れます。軽度であれば抗菌薬や洗浄によって改善することもありますが、慢性化した場合は上顎洞の穿孔閉鎖術やインプラントの除去が必要になるケースもあります。上顎洞への影響が疑われるときには、耳鼻咽喉科との連携が不可欠です。
副鼻腔炎
上顎洞炎が拡大すると、篩骨洞・前頭洞・蝶形骨洞などほかの副鼻腔へ炎症が波及し、副鼻腔炎として全身症状を呈することがあります。副鼻腔全体に及ぶ炎症は、いわゆる慢性副鼻腔炎(蓄膿症)に移行することもあり、鼻閉、頭痛、嗅覚低下、発熱、全身倦怠感などを伴います。特に免疫力が低下している患者さんや、既往に鼻疾患を抱えている方では、感染が重症化しやすく、歯科領域からの病因アプローチだけでなく、耳鼻科的な治療介入も同時に必要になることがあります。
副鼻腔炎はその原因が口腔由来であることに患者さん自身が気付かないことも多く、医師側も多角的視点で診断を行うことが重要となります。歯性感染症としての副鼻腔炎は、治療の遅れによって生活の質を著しく下げるため、早期対応が重要とされています。
トラブルに気付いた際に取るべき行動
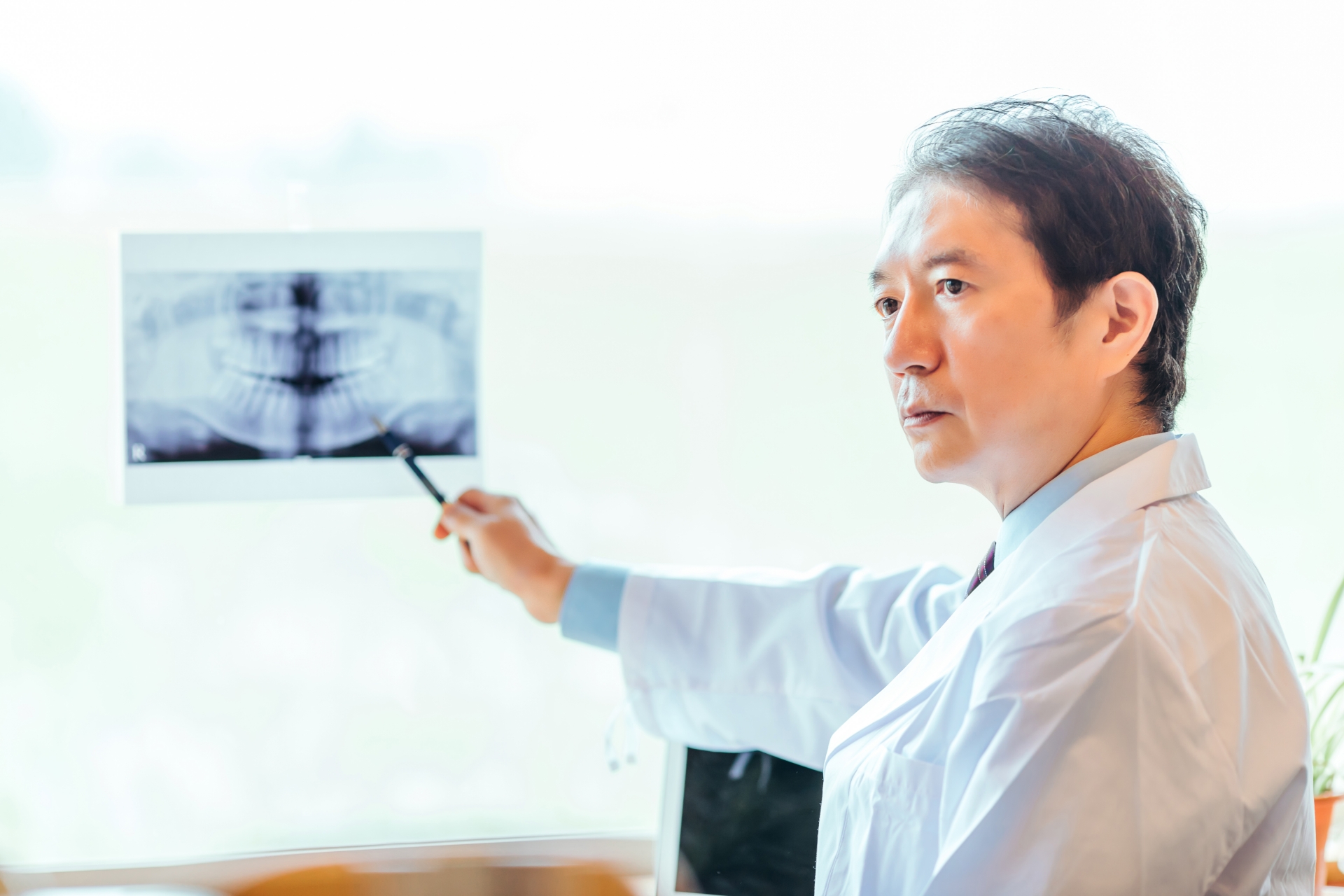 インプラント手術後のトラブルを自覚したら、以下の行動を取るようにしてください。
インプラント手術後のトラブルを自覚したら、以下の行動を取るようにしてください。
すぐに歯科医院へ連絡する
インプラント治療後に異常な出血、強い痛み、腫れ、しびれなどの症状に気付いた場合は、速やかに施術を受けた歯科医院へ連絡することが重要です。特に、インプラント体が顎の骨を突き抜けている可能性がある場合、放置すれば感染の進行や神経障害などを招きかねません。症状の程度に関わらず、我慢したり自己判断で市販薬を使用したりするのではなく、必ず医師の診察を受け、CTなどの画像診断を行って、トラブルの範囲や深刻度を把握する必要があります。
なかには、初期には軽い違和感程度であっても、数日後に強い腫脹や膿の排出などを呈するケースもあり、早期の対応が予後に大きく影響します。連絡の際には、症状が始まった頃や状況、治療後の経過についても正確に伝えるようにしましょう。
出血時は清潔なガーゼで圧迫止血し安静を保つ
インプラントを埋入した部位からの出血に気付いた場合は、まず清潔なガーゼやティッシュなどで出血部を軽く押さえ、圧迫止血を行いながら安静を保つことが推奨されます。口腔内の血管は豊富な血流を持つため、出血が止まりにくいことがありますが、焦らずに10〜15分程度は継続して圧迫を続けてください。
このときに強く噛みすぎて顎やインプラント周囲を過度に刺激するのは避けましょう。また、うがいや強い吐き出し動作は血餅(けっぺい)形成を妨げ、かえって出血を悪化させるおそれがあります。血が止まらない、もしくは大量に流れ出るような場合には、歯科医院や口腔外科をすぐに受診する必要があります。特に、血液疾患や抗凝固療法を受けている患者さんでは、止血処置に時間がかかることがあるため、主治医への報告も欠かせません。
痛みや腫れ、麻痺の経過を記録する
インプラント埋入後に現れた症状の推移を正確に記録することは、トラブルの診断と適切な対応を行ううえでとても重要です。例えば、痛みの発症した時刻やその強さ、腫れの部位や拡がり方、しびれがどの範囲に及ぶかなどを、時間ごとに簡潔にメモしておくと、診察時の問診で有益な情報となります。特に知覚麻痺や感覚異常に関しては、いつから症状が出現したか、どのような刺激に反応しないのか、症状は持続しているのかといった細かい情報が、神経損傷の部位や程度を推測する手がかりになります。
また、発熱や倦怠感、膿の排出といった全身症状も併せて記録しておくことで、感染の拡がりや重症度の評価にも役立ちます。こうした記録は、受診時に医師とのコミュニケーションをスムーズにし、迅速な治療選択を促す材料となります。
トラブルが起きた際の治療方法
 最後に、インプラント手術で貫通トラブルが起きた場合の治療法を解説します。
最後に、インプラント手術で貫通トラブルが起きた場合の治療法を解説します。
インプラントを抜去する
インプラントが骨を貫通して神経や粘膜、上顎洞などに影響を及ぼしていると判断された場合、そのまま埋入を維持することは困難です。症状の重篤化や周囲組織の損傷を避けるため、インプラント体の抜去(エクスプラント)が必要となります。
抜去処置は局所麻酔下で行われるのが一般的で、骨を削除してインプラントを除去したうえで、必要に応じて創部の縫合や感染対策を行います。骨造成を伴う処置が同時に検討されることもあります。また、抜去後はインプラント再埋入まで数ヶ月の治癒期間を設けることが多く、その間に骨の回復状態や周囲粘膜の健康状態を観察する必要があります。再治療にあたっては、同じ部位の再利用が困難なこともあるため、骨造成やインプラント位置の変更を含めた慎重な再計画が不可欠です。
外科的処置を行う
インプラントが貫通した先が上顎洞や鼻腔であった場合、周囲に炎症や感染が波及していることもあり、抜去だけでなく周囲組織へのアプローチが必要となる場合があります。
例えば、上顎洞炎や鼻腔底穿孔が確認されたケースでは、耳鼻咽喉科との連携のもと、病巣の掻爬、粘膜の縫合、洞粘膜の再建などが行われることもあります。炎症が慢性化している場合には、開窓術や副鼻腔洗浄などの処置も検討されます。膿瘍形成や骨髄炎を伴っている場合は、感染巣を外科的に除去したうえで、局所の洗浄やドレナージ処置を併用し、全身への感染拡大を防ぐ必要があります。骨内病変への介入は慎重さが求められるため、口腔外科医の管理のもとで対応が進められます。
神経損傷がある場合は薬物療法も
下顎部で下歯槽神経が損傷された場合、インプラント体の除去に加えて、薬物療法を併用することが多くあります。神経障害による症状には、しびれ、知覚低下、異常感覚などがあり、これらの症状は神経再生過程で一時的に増強することもあるため、長期的視点での管理が必要です。
薬物療法には、神経の修復や血流改善を目的としたビタミンB12製剤や末梢神経機能改善薬、さらには神経因性疼痛に対応する薬剤が用いられることがあります。特に慢性的な知覚麻痺を伴う場合には、ペインクリニックでの神経ブロックや電気刺激療法などが検討されることもあり、必要に応じて多診療科との連携が求められます。
まとめ
インプラントの貫通トラブルは、骨量の不足や術前診査の不備、埋入技術の問題などが重なって生じる可能性があります。特に上顎洞や下顎管、鼻腔底といった解剖学的リスク部位では、注意深い診断と計画が不可欠です。トラブルが発生した際は、早期に歯科医院へ連絡し、適切な診察と処置を受けることが重要です。症状の記録や自己管理も予後に大きく影響します。原因を的確にとらえ、必要に応じてインプラントの抜去や外科的対応、薬物療法を行うことで、患者さんの負担をできる限り少なくすることが可能となります。
参考文献
