インプラント治療は身体に負担がかかる手術が必要であることもあり、高齢の方が治療を受けられるのかどうかを心配するケースもあるのではないでしょうか。
この記事では、高齢者がインプラント治療を受けることができるかどうかや、治療の際に健康保険や補助金などを利用できるのかといった点について解説します。
高齢者でもインプラントを受けることができる?

インプラント治療は、手術によって人工歯根(インプラント体)を顎の骨に埋め込み、その上から人工の歯をかぶせるという治療法です。
手術の際には麻酔も必要で、歯科治療のなかでは大がかりな治療内容のため、身体への負担が大きくなりやすいといえます。
そのため、特に高齢者のように体力が低下しているような方の場合、治療を受けられないケースがあります。
また、人は加齢に伴って身体の回復能力が低下していくため、治療を受けることはできても、高齢者の場合にはさまざまなリスクが生じる可能性があります。 高齢者の方の場合、全身的な健康度合いやインプラントを行うために必要な付加処置によっては身体への負担が懸念されることがありますので、十分な検査を受け、身体に負担の少ない方法を慎重に判断されることをおすすめします。 まずは、高齢者の方がインプラント治療を受ける場合のリスクや、高齢者の方でも受けやすい治療法について紹介します。
高齢者がインプラントを受ける場合のリスク
高齢者の方がインプラントを受ける場合、下記のようなリスクが考えられます。 手術の身体的な負担によるトラブル 細菌感染などのリスク 治療期間が通常よりも長くなる まず第一に、高齢者の場合は体力が低下しているため、麻酔や手術そのものの身体への負担による合併症のリスクが高くなります。
特に、高血圧などの症状がある方の場合は手術によるリスクが高くなるため、治療を受けることができるかどうかは、歯科医師としっかり相談しましょう。 また、手術の後の経過についても、高齢者の方が治療を受ける場合にはリスクが生じやすいといえます。
その一つが細菌感染で、高齢者の方は若い頃と比べるとどうしても免疫力が低いため、手術後の細菌感染が引き起こされやすくなります。治療後に細菌感染が生じて手術部位に膿などが溜まってしまうと、治療の中止ややり直しになる可能性もあります。 さらに、加齢によって身体の代謝が低下していることから、埋め込んだインプラント体の結合や切開した粘膜の治癒にも時間がかかり、治療期間が通常より長くなるという点もリスクの一つです。
高齢者でも受けやすいインプラント治療
上記のように、高齢者の方がインプラント治療を受ける場合はさまざまなリスクがあり、治療方法によって利用しやすいものとそうでないものがあります。
例えば、インプラント治療には1回法と2回法という二つの方法がありますが、1回法は切開した傷口から細菌感染が生じやすいというリスクがあるため、高齢者の方の場合は2回法であれば治療を受けやすいといえます。 また、インプラント治療は1本の人工歯根に対して1つの白い歯(上部構造)を取り付ける治療が一般的ですが、複数の歯がなくなってしまっている場合に、すべての歯でインプラント治療を行うと身体への負担が大きくなります。
そういった場合に利用しやすい治療法が、インプラントとブリッジの併用や、インプラントオーバーデンチャーと呼ばれる入れ歯です。
歯が欠損している場所のすべてにインプラント治療を行うのではなく、数本のインプラントを土台にして固定するブリッジや入れ歯を使用することで、手術の負担を軽減できるため、高齢者でも治療を受けやすくなります。
インプラント治療を受けられないケース

高齢者の方に限らず、下記に該当するような方はインプラント治療を受けられない可能性があります。
顎の骨の量が少ない
インプラント治療は、顎の骨に金属製の人工歯根を固定する治療法です。
そのため、そもそも顎の骨の量が少ない方の場合、インプラントをしっかりと固定しにくくなるため、治療を受けられない場合があります。
骨の量は加齢のほか、歯周病などでも減少する可能性があるため、歯周病によって歯が抜けてしまった場合はインプラント治療を受けにくいといえます。
また、顎の骨は刺激を受けないと痩せやすくなるため、歯が抜けた場所を入れ歯やブリッジによって補っていた場合、顎の骨が減少してインプラント治療を受けにくくなる可能性があります。
口腔内の状態が悪い
むし歯や重度の歯周病があるなど、口腔内の状態が悪い方は、インプラント手術の際に細菌感染を起こしてしまい、骨と人工歯根の結合がうまくできなくなる可能性があるため、治療を受けられない場合があります。
特に、インプラントにはインプラント歯周炎という進行の早い歯周病があるため、歯周病が残ったままインプラントを受けると、せっかく治療をしても、すぐにインプラントの状態が悪くなってしまうという可能性もあります。
重度の全身疾患がある
糖尿病を患っている方や、腎疾患で人工透析を受けているような方も、インプラント治療を受けられない可能性があります。 糖尿病については免疫力や抵抗力の低下がその理由で、手術後の回復が遅くなってしまうほか、細菌感染のリスクやインプラント歯周炎のリスクが高くなるためです。
腎疾患で人工透析を受けている方も同様で、免疫力の低下が一つの要因ですが、さらに人工透析を受けている方は手術によって細菌が体内の臓器に回ってしまうリスクもあるため、治療を受けることができません。
骨粗しょう症
骨粗しょう症は骨の密度や質が低下する病気で、加齢や女性ホルモンの影響によって骨を作る能力が低下すると引き起こされやすいとされています。
骨がもろくなるためインプラントをしっかり固定しにくいことから治療を受けられなくなる可能性があります。
また、骨粗しょう症の治療として使用している薬剤によっては、インプラントなどのお口の手術がきっかけとなって、薬剤性顎骨壊死(がくこつえし)という顎の骨を腐らせてしまう症状が発生する可能性が指摘されています。
基本的には骨造成などによって骨を強化することでインプラント治療が可能となりますが、治療が可能かどうかは歯科医師とよく相談することが大切です。
顎の骨が減っていてもインプラントを受ける方法

上述のように、インプラントは顎の骨に人工歯根を固定する関係で、顎の骨が減っていると治療を受けられない可能性があります。
しかし、下記のような対策を行うことで、顎の骨が減っていてもインプラント治療を受けることができるケースがあります。
骨造成を受ける
骨造成とは、その名前のとおり、骨を作り出す治療のことです。
実は、骨は常に一定の状態で体内に存在しているのではなく、細胞の働きによって常に破壊と再生が繰り返されています。
顎の骨が少ない方は、加齢などによって骨の再生力が低下し、破壊が進んでしまっている状態です。そのため、骨の再生を促進する薬剤を使用して骨の量を取り戻すことができれば、インプラント治療を受けられる可能性があります。
骨造成にはいくつかの治療法がありますが、共通している点は、インプラント治療を受けるために増強が必要な骨の周囲に骨補填材という骨の再生を促す材料を入れ、後はしっかりと新しい骨が作られるのを待ちます。
場合によってはインプラント治療と同時に骨造成が行われることもあり、治療したい歯の部位などによって対応方法が異なります。
ザイゴマインプラントを利用する
ザイゴマインプラントは、インプラントを顎の骨ではなく、頬骨に固定する治療法です。
通常のインプラントは、歯を支えている骨と同じ顎の骨(歯槽骨)に固定するため、顎の骨が痩せてしまうと治療が難しくなります。
一方でザイゴマインプラントは頬の骨に対して固定するため、顎の骨が痩せてしまっている方でも、治療を受けることが可能です。
ただし、頬骨に対して固定を行うため、対応が可能なのは上の歯だけです。
注意点として、インプラントを埋め込む位置が深くなるため、細菌感染などのリスクがより高くなる可能性があります。
インプラント治療を保険適用で受けることは可能?
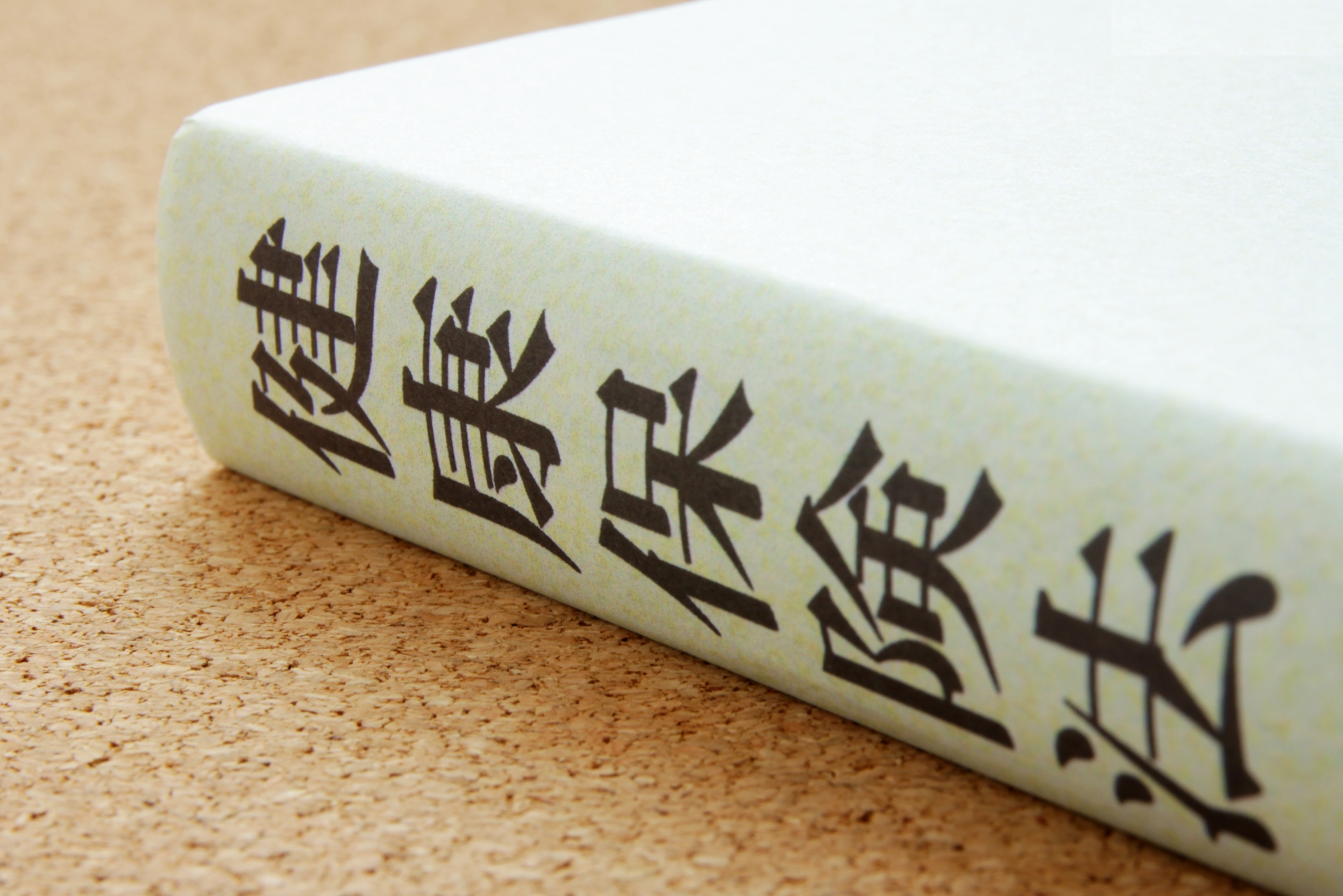
インプラント治療は、天然の歯と同じような噛み心地を実現可能であり、お口の機能を保つという点ではとても有用な治療です。
しかし、インプラント治療は治療費用が高額になりやすいという側面があり、これがインプラント治療を手軽に受けることができない要因の一つとなっています。
インプラント治療を受けたいという方のなかには保険適用で費用を抑えたいと考える方も多いと思いますが、実はインプラントは特殊なケースに限り、保険適用での治療が認められています。
保険適用でインプラント治療を受ける場合の治療費用は、3割負担の場合で1本あたり45,000円程度で、これに診断料や被せ物などの費用が追加されます。 インプラント治療を保険適用で受けることができるのは、下記のようなケースです。
腫瘍や事故の外傷が原因の場合
インプラントが保険適用となるケースの一つ目が、骨髄膜炎や口腔がんなどの病気、または事故による外傷が原因で顎の骨が広範囲にわたって欠損してしまった場合です。
顎そのものが欠損してしまうことにより、そもそも入れ歯やブリッジといったほかの治療によって噛み合わせの機能を回復させることが難しいことから、インプラント治療が保険適用として認められています。
生まれつきの疾患
先天的な疾患により顎の骨の3分の1以上が欠損していると診断されるケースや、顎の骨の形成不全がみられる場合にも、インプラントを保険適用で受けることができる可能性があります。 なお、上記のどちらのケースであっても、インプラントを保険適用で受けるためには治療を行う施設側も一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、入院用ベッドが20床以上ある病院であることや、当直体制が整備されていること、そして治療を行う歯科医師が病院で5年以上の治療経験を持つことなどが条件になるため、一般的な歯科クリニックで保険適用によるインプラント治療を受けることはできません。
インプラント治療に高額療養費制度は利用できる?

高額療養費制度とは、医療費が家計負担を圧迫しないよう、収入ごとに1ヶ月の間にかかる医療費の上限が設定され、その上限を超えた金額は払い戻しを受けることができるという制度です。
この制度によって、高額な医療費がかかるような病気をした場合でも、無理なく適切な医療を受けることができます。 ただし、この高額医療費制度は、保険適用の治療のみが対象となるため、基本的に自費診療で行われるインプラント治療の場合は対象となりません。
そのため、インプラント治療で高額な医療費がかかったとしても、その分の払い戻しを受けることはできません。 一方、似たような言葉の制度として、医療費控除というものがあります。
医療費控除は、所得税や住民税の計算をするための所得から、年間に支払った医療費の10万円を超える部分を控除することができるという制度です。
医療費控除を利用することで年間の所得金額が抑えられるため、所得税や住民税の支払いを少なくできる可能性があります。
インプラント治療に利用可能な補助金はある?
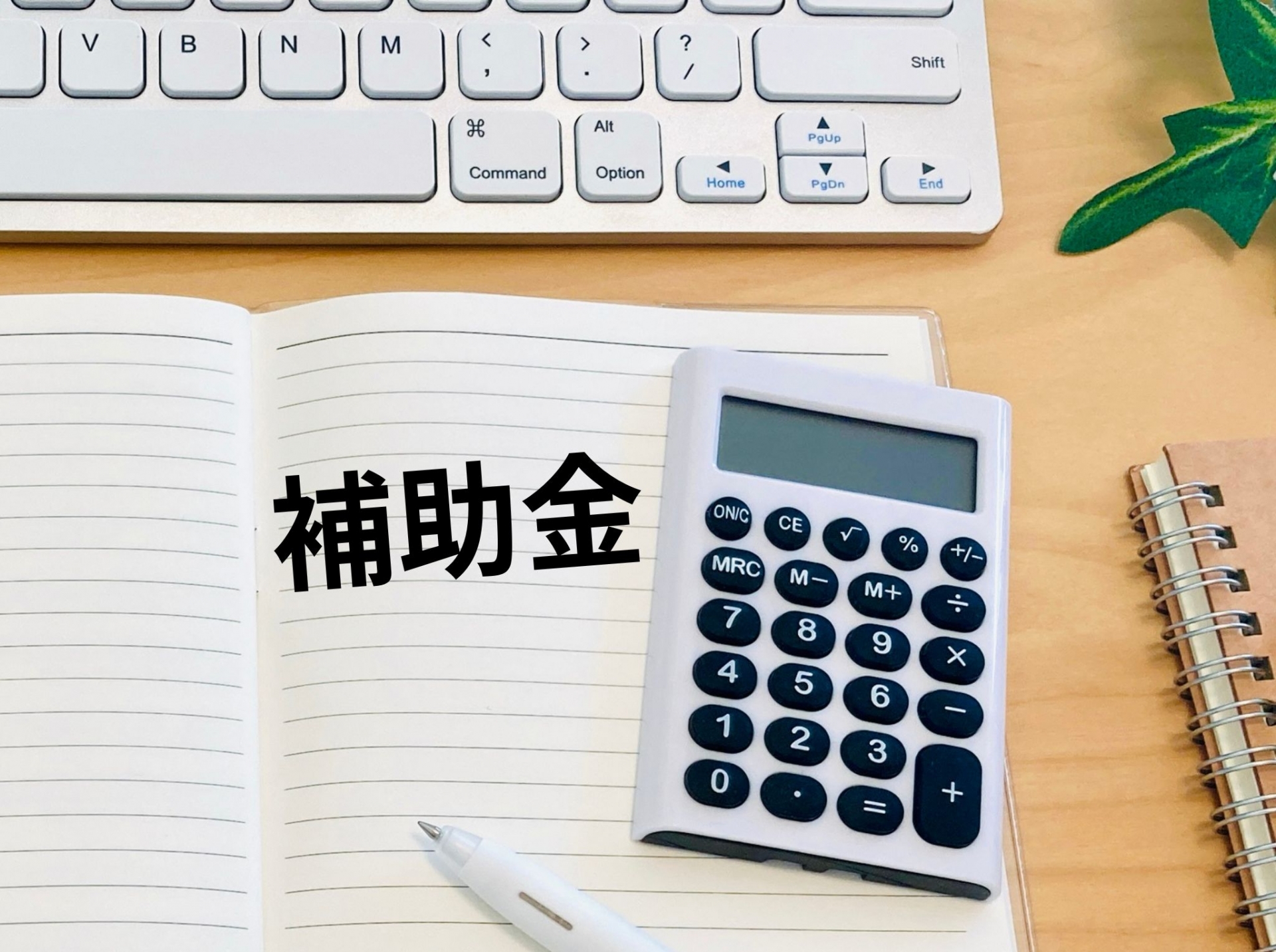
補助金とは、国や自治体がさまざまな目的で交付するお金のことで、例えば環境によい住宅を購入する際や、電気自動車の購入の際など、さまざまな補助金の制度があります。
補助金は各自治体などが予算に応じて使い道を決めているため、なかには住民の健康を維持するための目的で使用されているものもありますが、インプラント治療に利用可能な補助金はないと考えてよいでしょう。
まとめ

インプラント治療は、しっかりとした噛み心地を実現しやすくさまざまなメリットがある治療です。
しかし、インプラント治療は顎の骨に金属製のパーツを埋め込むという手術が必要になることから、手術そのものによる身体への負担や、細菌感染といったリスクが存在します。
高齢者の方や、糖尿病などの全身疾患を患っている方の場合、こうしたリスクの懸念からインプラント手術を受けられない可能性があります。
その他にも、インプラントは顎の骨の量が減少していると治療が行えないなどの特徴がありますので、治療に興味がある方は、一度歯科医院での検査を受けてみて、治療の適応となるかどうか歯科医師と相談してみるとよいでしょう。 なお、インプラント治療は高額になりやすいことから、健康保険や補助金を利用したいという方も多いと思いますが、インプラント治療は特殊な場合を除いて保険適用とならず、高額医療費制度や補助金を利用して治療費用を抑えることもできません。
ただし、インプラント治療は医療費控除の対象にはなりますので、少しでも治療費用を抑えたいという方は、医療費控除を活用してみるとよいのではないでしょうか。
参考文献
