サイナスリフトは、インプラント治療を検討する際の骨量不足を補うために行われる、骨造成術の一つです。加齢や抜歯後の骨吸収によって上顎洞が拡大し、インプラント埋入に必要な骨量が確保できないケースがあります。そのような場合、上顎洞底を持ち上げて骨補填材を挿入し、人工的に骨の高さと厚みを増加させることで、インプラントが安定して支持される環境を整えます。しかし、術後に上顎洞炎を発症するリスクがあることをご存じでしょうか。この記事では、サイナスリフトの基礎知識から、上顎洞炎のリスクとその予防法、万が一発症した場合の対処法まで詳しく解説します。
サイナスリフトの基礎知識
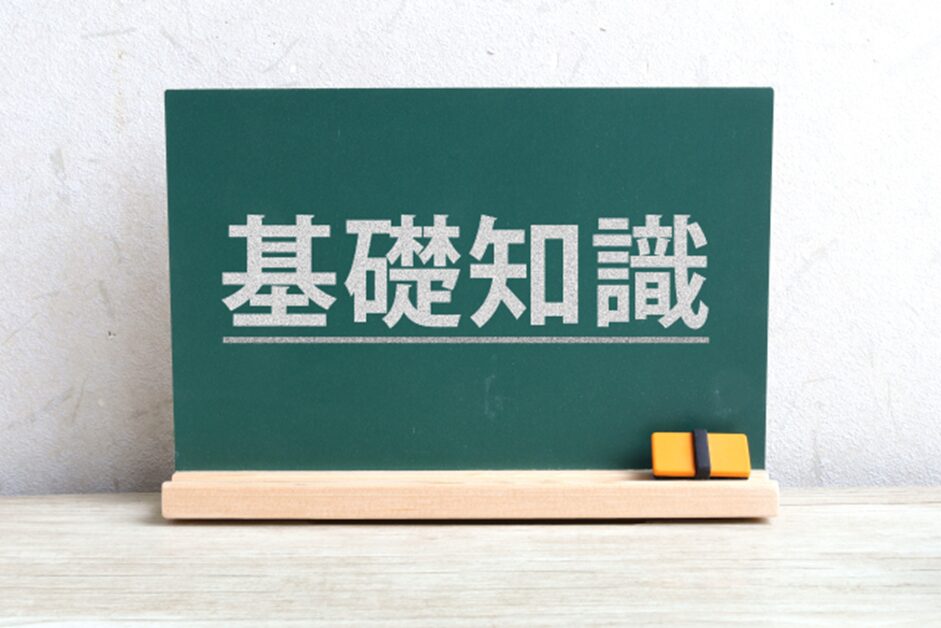
サイナスリフトはインプラント埋入を目的とした骨造成術の一つです。ここでは、サイナスリフトの目的や施術の流れなど、基本的な情報について解説します。
サイナスリフトの目的
サイナスリフトとは、上顎にインプラントを埋入するうえで、必要な骨の厚みが不足している場合に行われる骨造成術の一種です。特に上顎の臼歯部領域は、加齢や歯の喪失後に骨が吸収されやすく、さらに上顎洞と呼ばれる空洞が拡大してくることがあります。このような状態では、インプラントを十分に固定できるだけの骨が存在しないため、サイナスリフトを行うことで人工的に骨を増やし、安定した土台を作る必要があります。
施術の流れと特徴
サイナスリフトは、上顎臼歯部の歯肉を切開して骨面を露出し、上顎洞の側壁に骨窓と呼ばれる開口部を作るところから始まります。続いて、上顎洞内の粘膜(シュナイダー膜)を破れないよう慎重に剥離し、上方に持ち上げてスペースを作ります。そのスペースに、自家骨や人工骨、異種骨などの補填材を注入して骨造成を行います。補填材は時間とともに新しい骨へと置き換わり、インプラントを安定させる土台となります。
一般的に骨造成後、数ヶ月の治癒期間を経て二期的にインプラントを埋入しますが、条件が整っていればサイナスリフトと同時にインプラントを埋入することもあります。
上顎洞とその役割

サイナスリフトを理解するには、まず上顎洞の構造について理解しておくことが大切です。ここでは上顎洞の構造や歯科治療との関係について詳しく説明します。
上顎洞の構造
上顎洞は前頭洞、篩骨洞、蝶形骨洞とならぶ副鼻腔の一つで、左右の頬骨の奥、鼻腔の側面にある空洞です。内側はシュナイダー膜という粘膜で覆われ、鼻腔と自然孔を通じてつながっています。上顎洞は空気で満たされ、頭部の軽量化や呼吸時の共鳴、吸気の加温・加湿、分泌物の排出など、複数の役割を果たしています。
この粘膜には線毛が密集し、異物や分泌液を鼻腔へ排出する機能がありますが、炎症が起こると排出が滞り、上顎洞炎の原因になります。
歯科治療との関係
歯の根尖病変や抜歯、インプラント治療などの歯科処置は、上顎洞と深い関わりがあります。特に上顎の大臼歯や小臼歯は、歯根が上顎洞に近接または突出していることが多く、炎症が歯槽骨を介して上顎洞に波及し、上顎洞炎の原因となることがあります。
サイナスリフトのように上顎洞に直接アプローチする手術では、上顎洞粘膜(シュナイダー膜)の損傷に注意が必要です。この粘膜を損傷すると細菌が侵入しやすく、感染や異物反応のリスクが高まります。
そのため、術前にはCTによる詳細な評価が不可欠です。上顎洞の形態や粘膜の厚さ、骨の高さ、自然孔、既存病変の有無などを確認し、慎重な手術計画を立てることが求められます。術中に膜が穿孔した場合も、適切な閉鎖処置や手術の延期といった判断が重要です。
なぜサイナスリフト後に上顎洞炎が起こるのか

サイナスリフト後に上顎洞炎が発生する主な原因には、上顎洞粘膜(シュナイダー膜)の損傷、骨補填材の上顎洞内への迷入、術後の感染管理の不備が挙げられます。
特に粘膜の穿孔は、細菌侵入の原因となり、補填材が上顎洞内に迷入すると異物反応や炎症を引き起こす恐れがあります。また、術後の口腔衛生不良や抗菌薬の服用忘れ、強く鼻をかむといった行為も感染リスクを高めます。
喫煙歴や糖尿病の既往、術前から上顎洞内に炎症や嚢胞を有する患者さんでは、粘膜の排出機能が低下し、炎症が悪化しやすくなります。また、自然孔の閉鎖、鼻中隔の湾曲や鼻腔の狭窄などの解剖学的異常も、術後の換気不良を引き起こす要因です。このように、サイナスリフト後の上顎洞炎は単一の要因ではなく、術中の損傷、補填材の取扱い、術後管理、解剖学的背景、全身状態など複数の要因が重なって発生する合併症です。
上顎洞炎の症状と重症化のリスク

上顎洞炎では上顎洞の粘膜に炎症が生じる状態で、初期には軽い鼻づまりや頬の違和感といった症状にとどまることが多いものの、放置すると重症化することがあります。ここでは、上顎洞炎の症状と重症化を防ぐために知っておくべきポイントについて解説します。
初期症状の見分け方
術後、頬の痛みや腫れ、鼻づまり、鼻汁、頭重感といった症状が現れた場合、上顎洞炎の可能性があります。鼻汁は片側から出ることが多く、黄色~緑色の膿のようなもので悪臭を伴うこともあります。感染が広がり、症状が進行すると、発熱、悪寒、倦怠感、食欲低下など全身症状が出ることもあります。歯の違和感や痛みが出ることもあり、特にインプラント部に圧痛や鈍痛がある場合、周囲の骨に炎症が及んでいる可能性があります。
CT検査などで早期に診断を受け、適切に治療することが大切です。早期の対応により、炎症の慢性化やインプラントへの悪影響を防ぐことができますので、上記症状を認めた場合は、早めに担当医に相談してください。
放置による合併症のリスク
上顎洞炎を放置すると、膿が自然口から排出されずに閉塞し、炎症が上顎洞と連続する前頭洞や篩骨洞に広がる可能性があります。慢性化すると粘膜が肥厚し、鼻づまりや後鼻漏、頭重感など、日常生活に支障をきたす症状が長引くことになります。
さらに感染が骨に及ぶと、上顎骨骨髄炎やインプラント周囲炎といった重篤な合併症を引き起こすことがあり、場合によっては外科的な処置が必要になります。インプラント周囲の骨が吸収されると、インプラントの脱落に至ることもあります。
特に高齢者や糖尿病患者さんでは重症化しやすく、ときには命に危険をもたらす可能性もあるので注意が必要です。軽度の症状でも早期の診断と治療が、重大な合併症を防ぎ、インプラントの安定にもつながります。
サイナスリフト手術前に確認しておくべきこと

サイナスリフトを安全に行ううえで、術前に確認しておくべきことがいくつかあります。ここでは、そのポイントについて解説していきます。
既往歴と解剖学的条件
サイナスリフトを安全に行うためには、術前の詳細な画像診断と耳鼻科的評価が極めて重要です。特にCT画像から得られる情報は、上顎洞の三次元的な構造把握に有用です。上顎洞の炎症や粘膜肥厚、自然孔の開存状態、骨の厚み、隔壁の有無、上歯槽動脈の走行などを正確に評価できます。
また、過去に副鼻腔炎を繰り返していた方や慢性的な鼻づまり、鼻中隔の湾曲、アレルギー性鼻炎などの既往がある方では、上顎洞の換気や排出機能が低下していることが多く、術後に上顎洞炎が発生するリスクが高まります。これらのリスクを最小限に抑えるためには、術前に耳鼻科での評価を受け、必要に応じて炎症の治療や鼻中隔矯正術、内視鏡下副鼻腔手術の先行も検討されます。
こうした画像診断と多診療科連携を通じて、サイナスリフトの計画と安全性が大きく向上し、インプラント治療の長期的な成功にもつながります。
感染リスクを下げるための対策
サイナスリフト手術では、上顎洞に直接アプローチするため、術後感染のリスクをいかに下げるかが重要なポイントとなります。そのため、医療者側による適切な感染管理が欠かせません。
まず基本となるのが、術前・術後の抗菌薬投与です。患者さんの全身状態や口腔内の清潔度を考慮し、広範囲に作用する抗菌薬を適切なタイミングで処方・投与することで、創部や上顎洞への感染を予防します。特に糖尿病や免疫力が低下している方では、重症化のリスクが高まるため、より慎重な管理が求められます。
さらに、術前には歯周病やむし歯、根尖病変の有無を確認し、必要に応じて歯石除去やむし歯処置などの口腔ケアを行うことも大切です。これにより、口腔内の細菌数を事前に減らし、術後の感染リスクを抑えることができます。
術後のフォローも重要です。腫れや発赤、排膿、発熱など、感染の兆候を早期に察知し、必要に応じて抗菌薬の再投与や局所の処置を速やかに行うことで、合併症を未然に防ぎます。このように、手術前から手術後までの医療者側の対応が、サイナスリフトの成功と安全性を大きく左右します。
サイナスリフト手術後の過ごし方のポイント

手術後の過ごし方によって回復のスピードや合併症のリスクが大きく変わります。安心して治療を進めるために、日常生活で気をつけるべきポイントやセルフケアの方法をわかりやすく解説します。
感染予防のためのセルフケア方法
医療者の処置に加え、術後のセルフケアも回復と感染予防に欠かせません。処方された抗菌薬や鎮痛薬は、指示どおりに服用し、自己判断で中止しないようにしましょう。
鼻を強くかむ、くしゃみをこらえる、ストローを使うなど、上顎洞の圧を高める行為は避けてください。くしゃみはお口を開けて行い、飛行機や高地への移動も術直後は控えましょう。
喫煙や飲酒は傷の治癒や感染に悪影響を及ぼすため、術後は避けるのが望ましいです。激しい運動や長時間の入浴も控え、寝るときは頭を少し高くして仰向けにすると腫れの予防になります。
食事はやわらかく刺激の少ないものを選び、うがいは優しく行いましょう。こうした日常の工夫が、術後の経過を良好に保つ鍵となります。
歯科医院を定期的に受診する
術後の経過中に、強い痛みや腫れ、発熱、出血、鼻から液体が出るなどの異常が見られた場合は、すぐに歯科医院や口腔外科に相談してください。まれに上顎洞炎や感染が生じるため、早期の対応が重要です。
術後の通院は治癒の確認と感染予防のために欠かせません。見た目に問題がなくても、必ず医師の指示にしたがって定期的に受診し、術後経過をしっかりと見守りましょう。
上顎洞炎になった場合の治療方法
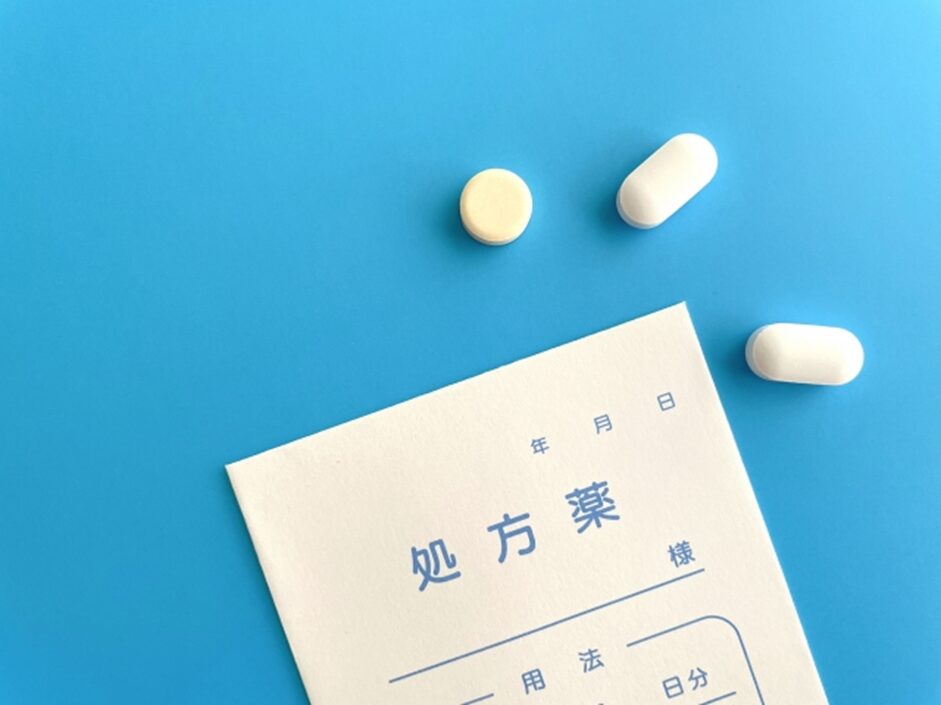
上顎洞炎は、サイナスリフト後に生じうる合併症です。痛みや膿が出るなどの症状がある場合は、早めの治療が大切です。ここでは、上顎洞炎の主な治療法と受診の目安について解説します。
抗菌薬による治療
軽度の上顎洞炎であれば、抗菌薬の内服で改善することが多いです。鼻腔洗浄や点鼻薬を併用することで、排膿を促し治癒を早めます。
外科的処置による治療
薬物療法で改善しない場合は、上顎洞へのドレナージや、内視鏡手術などの外科的処置によって病変部を除去することがあります。インプラントや骨補填材の除去が必要になることもあるため、早期の対応が重要です。
手術前後の適切な対応でトラブルを防ぐ

サイナスリフトはインプラント治療において重要な選択肢ですが、術後合併症のリスクもあります。患者さん自身がリスクと予防法を理解し、歯科医と連携して適切な対応を行うことで、合併症の発生を最小限に抑えることが可能です。
まとめ
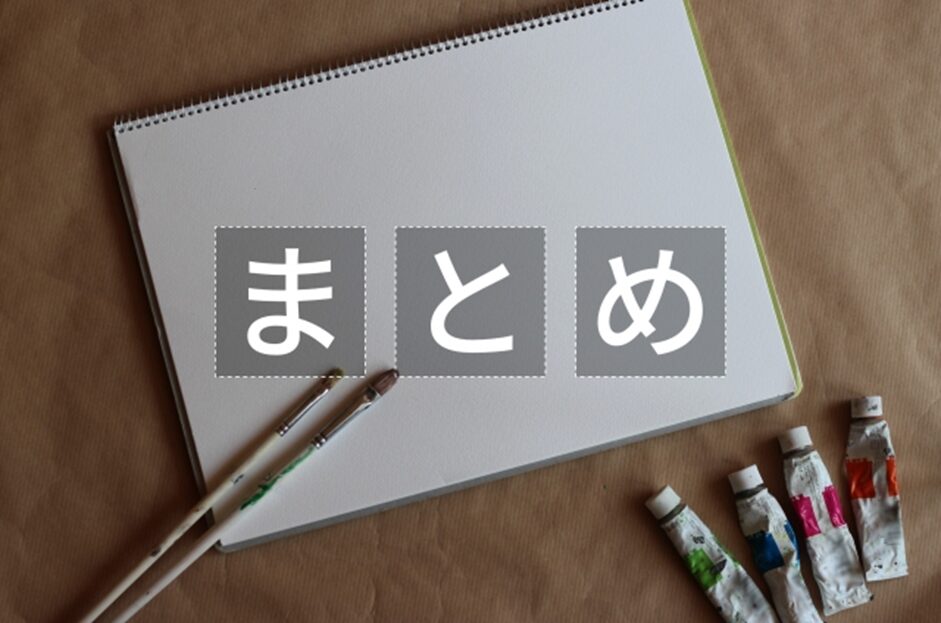
サイナスリフトは骨量の不足した上顎臼歯部へのインプラント治療に欠かせない技術ですが、上顎洞炎という合併症のリスクも伴います。手術前の精密な評価と計画、術後の適切なセルフケアと医療機関のフォローが、安心・安全な治療につながります。不安な点がある場合は、専門医に相談し、納得のいく形で治療に臨みましょう。
参考文献
- 口腔インプラント治療指針2016 医歯薬出版, 2016.
- ビジュアル歯科臨床解剖 基礎から応用まで クインテッセンス出版株式会社,2020.
- サイナスリフトをより安全で確実に行うための難易度分類
- 上顎洞底挙上術 —側方アプローチと歯槽頂アプローチ
