インプラント治療は、噛み合わせや審美性の回復に優れた方法としてたくさんの患者さんに選ばれています。しかし一方で、ごくまれに味がしない、味が変わったといった味覚障害を訴えるケースも報告されています。こうした異常は一時的なものであることが多いものの、原因や背景を正しく理解しておくことが大切です。本記事では、インプラント治療と味覚障害の関係性や原因、予防のためにできることについて解説します。
インプラントと味覚障害の関係性
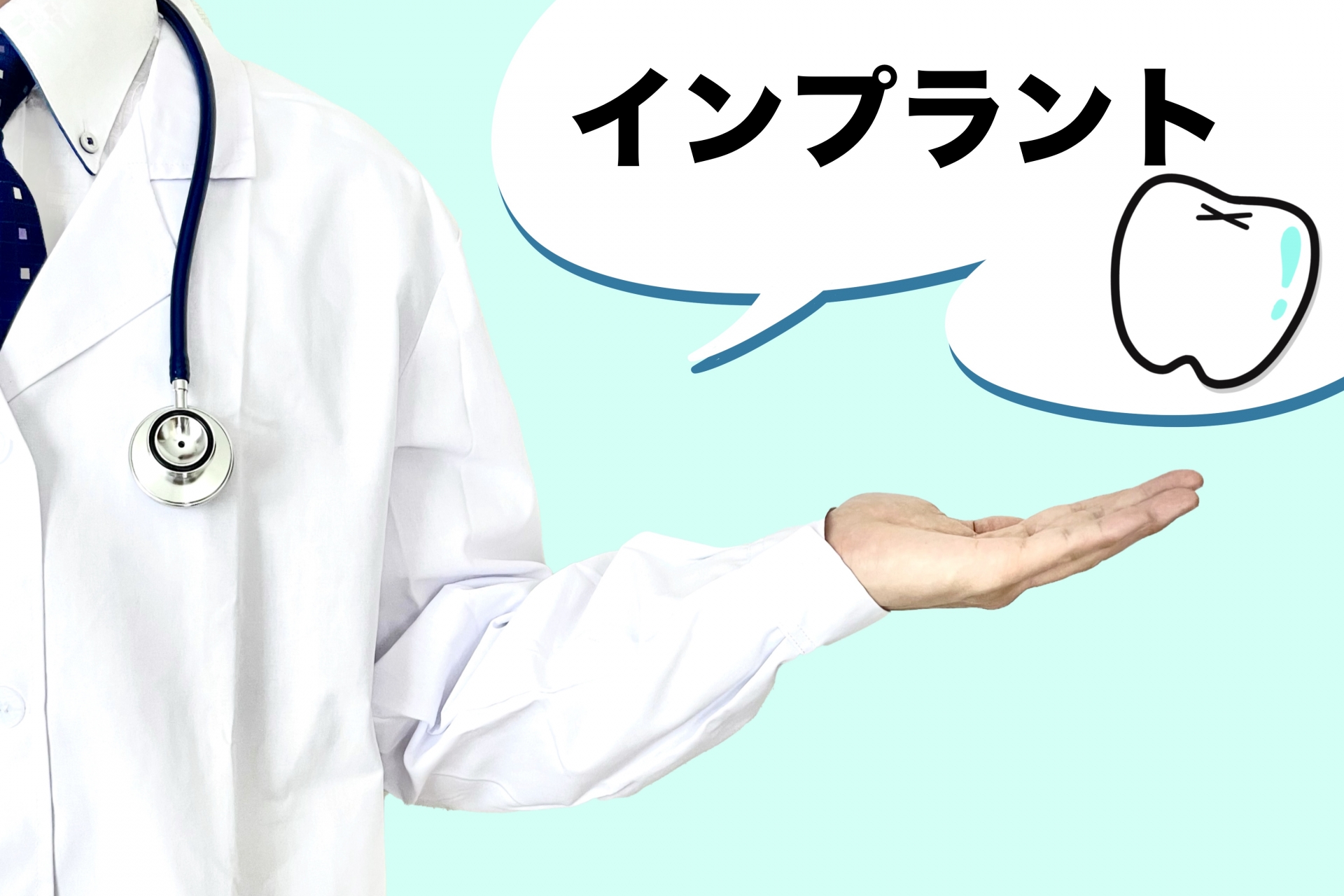 はじめに、インプラント治療と味がしないという症状との関係性について解説します。
はじめに、インプラント治療と味がしないという症状との関係性について解説します。
- インプラント治療が味覚に影響を与えることはありますか?
- インプラント治療が直接味覚に影響を及ぼすことは多くありませんが、まれに味覚障害が見られるケースがあります。インプラント手術の際、上顎や下顎に分布する神経に何らかの刺激や圧迫が加わった場合、味を感じにくくなることがあります。特に下顎の臼歯部に埋入する場合、舌の感覚や味覚に関わる舌神経や鼓索神経に近接しているため、神経に接触や損傷が生じると味覚に影響が出ることがあります。ただし、ほとんどの場合は一時的な感覚異常であり、時間の経過とともに改善する傾向があります。術前にCTなどの検査を行い、神経の走行を正確に把握することで、このようなリスクを回避することが可能です。
- 一時的な影響である場合、味覚はどのくらいの期間で戻りますか?
- インプラント手術後に一時的な味覚異常が生じた場合、通常は数週間から数ヶ月のうちに自然に回復することが多いとされています。これは、神経に軽微な圧迫や炎症が加わったことで起こる一過性の神経障害によるものであり、神経の損傷が軽度であればあるほど、回復は早くなります。特に手術後1〜3ヶ月の間に感覚の回復が見られるケースが多く、徐々に味の感覚が戻ってきます。しかし、6ヶ月を過ぎても改善が見られない場合には、神経に中等度以上のダメージが及んでいる可能性も考えられるため、歯科医師による精査が必要です。術後の経過観察を継続し、回復の兆候を丁寧に確認することが大切です。
- 入れ歯とインプラントで味覚への影響に違いがあるのか教えてください
- 入れ歯とインプラントでは、味覚への影響に明確な違いがあります。入れ歯は、床と呼ばれる装置が上顎や下顎の粘膜を広く覆うため、味蕾(味を感じる細胞)への物理的な刺激が減少し、味を感じにくくなることがあります。さらに、装着による違和感や唾液の分泌量の変化も、味覚の感受性に影響を与える要因となります。一方、インプラントは顎の骨に直接固定されるため、粘膜や味蕾を覆うことがなく、お口の感覚も自然に保たれやすいです。そのため、入れ歯よりも味覚の保持には有利といえるでしょう。ただし、インプラントでも手術に伴う神経への影響によって一時的に味覚が変化することがあるため、治療内容に応じた説明と術前の診断が重要です。
インプラント治療後に味がしないと感じる原因
インプラント治療を受けた後に味がしないという症状が現れた場合の原因について解説します。
- 麻酔や手術後の炎症が味覚障害の原因になることはありますか?
- 麻酔や手術後の炎症が味覚に一時的な影響を及ぼすことはあります。特に下顎のインプラント手術では、局所麻酔が舌神経やその近くに投与されることがあり、この神経は舌の前方2/3の味覚と触覚に関わるため、麻酔の影響で一時的に味を感じにくくなる場合があります。また、手術後の炎症反応によって周囲の神経が腫れや浮腫により圧迫されると、味覚に違和感が生じる可能性もあります。これらの症状は多くの場合、一時的なものであり、炎症が治まり、神経が回復することで自然に改善します。ただし、強い痛みや感覚の異常が続く場合は、速やかに歯科医師に相談する必要があります。
- 治療中のストレスや心因的要因が味覚に影響を及ぼすことはありますか?
- ストレスや心理的要因が味覚に影響を与えるケースもあります。インプラント治療は外科的処置を伴うため、治療への不安や緊張、術後の経過に対する心配などが重なり、自律神経のバランスが乱れることがあります。自律神経は唾液分泌や味覚にも関与しており、過度なストレスは味覚低下や味覚異常の一因となることが知られています。また、ストレスによって口腔乾燥が生じると、唾液中に含まれる味物質が味蕾に届きにくくなり、味を感じにくくなることもあります。このような場合は、身体の回復とともに味覚も改善することが多いため、十分な休息や心理的サポートも重要です。
- 手術時の神経損傷によっても味覚障害が起きますか?
- 手術時に神経を損傷した場合、稀ではありますが味覚障害が生じることがあります。特に下顎の臼歯部にインプラントを埋入する際、舌神経やその枝である鼓索神経に近接する部位では、注意が必要です。神経が直接傷ついた場合、舌の一部で味を感じなくなったり、しびれが生じたりすることがあります。損傷の程度が軽ければ数週間から数ヶ月で自然回復しますが、神経線維が切断された場合は、完全な回復が難しくなることもあります。こうしたリスクを抑えるために、事前にCT撮影などで骨の厚みや神経の走行を正確に把握し、十分な余裕を持ってインプラントを埋入することが不可欠です。
- 味覚に異常がある場合、加齢やほかの病気の影響も考えられますか?
- 味覚の異常はインプラント治療に限らず、加齢や全身疾患、薬の副作用などによっても生じることがあります。加齢に伴い、味蕾の数が減少し、味を感じにくくなる傾向があります。また、糖尿病や甲状腺疾患、亜鉛欠乏なども味覚異常の原因となることがあります。服用している薬剤、例えば降圧薬や抗うつ薬の一部にも、味覚への影響が知られています。インプラント治療後に味覚の変化があった場合でも、それが歯科治療によるものとは限らず、背景に別の要因が潜んでいる可能性もあるため、必要に応じて内科的な検査を受けることも検討されます。歯科と医科の連携による包括的な診断が重要です。
インプラント治療後にできる感覚異常の予防方法

- 定期的にメンテナンスを受けるとインプラント周囲炎やそれにまつわる感覚異常を防げますか?
- 定期的なメンテナンスは、インプラント周囲炎の予防と、それに伴う感覚異常の発症リスクを低下させるうえで重要です。インプラント周囲炎は、歯茎の腫れや出血から始まり、進行すると顎の骨の吸収やインプラントの動揺に至ることもあります。この炎症が神経の近くで起こると、腫れや感染によって神経が圧迫され、しびれや違和感などの感覚異常が生じることが稀にあります。定期的な歯科医院でのメンテナンスでは、インプラントの清掃状態や歯茎の状態、骨の吸収の有無を継続的に評価し、早期の炎症兆候を見逃さずに対処することが可能です。また、噛み合わせの変化による過剰な力がかかっていないかどうかも確認できるため、メンテナンスは単に清掃にとどまらず、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。
- インプラント治療後に自宅でできるインプラント周囲炎や感覚異常への対策方法があれば教えてください
- インプラント治療後の自宅でのケアは、インプラント周囲炎や感覚異常の予防において基本となります。最も大切なのは、毎日の丁寧な口腔清掃です。歯ブラシだけでなく、フロスや歯間ブラシ、場合によってはワンタフトブラシなどの補助清掃用具を併用し、インプラント周囲にプラークが蓄積しないようにしましょう。特にインプラントは天然歯と異なり、歯根膜が存在しないため、炎症が進行しやすい傾向があります。また、喫煙はインプラントの予後に悪影響を与えるとされており、血流が悪くなることで免疫反応が鈍り、感染リスクが高まるため禁煙が強く推奨されます。さらに、身体の抵抗力を高めるためには、栄養バランスのとれた食生活と十分な睡眠、ストレスの軽減も意識したいところです。加えて、感覚に異常を感じた際には、自己判断せず早期に歯科医師へ相談することが、症状の進行を防ぐ第一歩となります。
- もし味覚障害が治らない場合は、何科を受診すべきですか?
- インプラント治療後に味覚障害が続く場合には、歯科のほかに耳鼻咽喉科や口腔外科の受診を検討するとよいでしょう。味覚をつかさどる神経は舌や耳の周囲、脳の中枢にまで分布しており、複数の要因が関与している可能性があります。歯科ではインプラント手術に関わる神経の状態や炎症の有無を確認できますが、長期間にわたって症状が改善しない場合は、全身的な要因や内科的疾患も視野に入れる必要があります。耳鼻咽喉科では、味覚に関わる神経の専門的な検査や、内服薬の影響なども含めた評価が可能です。また、原因が明確でないケースでは、神経内科や栄養内科との連携が求められることもあります。早期に適切な科を受診し、必要な治療を受けることが、回復への第一歩です。
編集部まとめ
インプラント治療における味覚障害は、神経への影響や炎症、ストレスなど、複数の要因が関わることがあります。正確な診断と丁寧な手術計画、術後のセルフケアや定期的なメンテナンスが、こうしたリスクの軽減に役立ちます。万が一、味覚に異常を感じた場合には、自己判断せずに早めに歯科や耳鼻咽喉科を受診しましょう。長く快適にインプラントを使用するためにも、全身とお口の健康を意識することが大切です。
参考文献
